
2025.08.24
インナーブランディングとは?進め方や成功事例などを紹介!
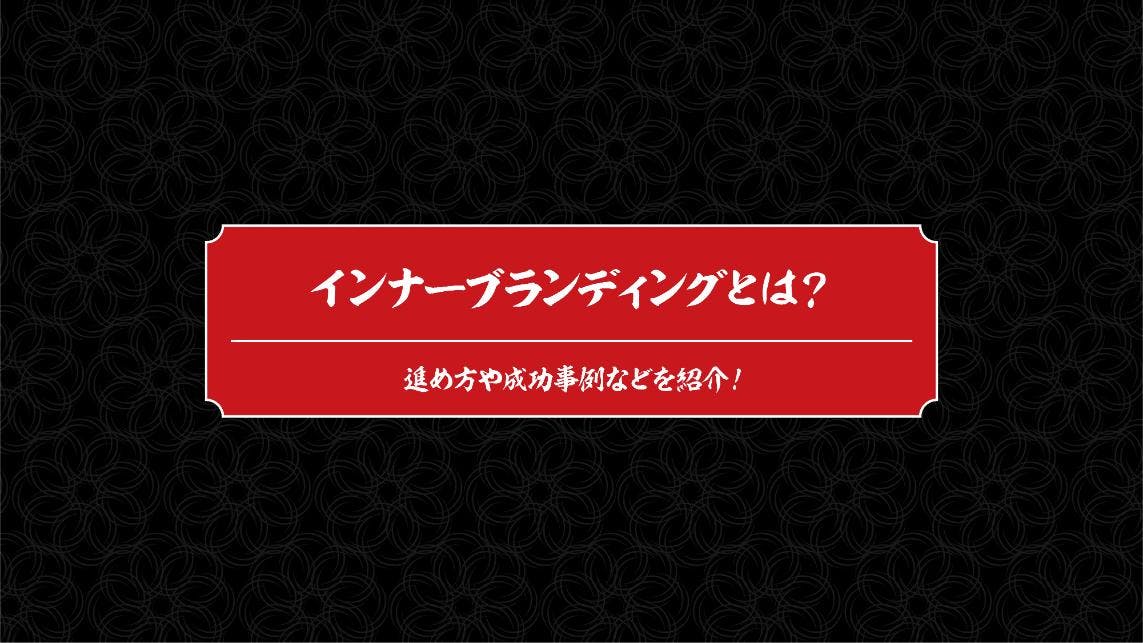
企業の成長やブランド価値の向上には、社外への発信だけでなく、従業員の意識統一も欠かせません。近年注目を集めている「インナーブランディング」は、社員の共感と行動を引き出し、企業理念を組織内に浸透させる取り組みです。
この記事では、インナーブランディングの意味や進め方、成功事例などを紹介します。社内改革やブランディングに課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
インナーブランディングとは?

インナーブランディングとは、企業理念やブランド戦略といった「思想」を社員と共有し、「共感」と「価値観の一致」を生み出すための仕組みやプロセスのことです。
単なる情報共有ではなく、社員一人ひとりがその思想を信じ、体現していく文化づくりを指します。この構造は、ある意味で宗教のようなものに近いといえます。
企業が目指す未来や理念を「信仰の対象」とし、それに共鳴した社員たちが、自主的に実践し続けることで、組織全体が同じ方向を向く状態がつくられます。
思想が浸透すると、従業員は企業に対して誇りを持つようになり、理念の実現に向けた小さな努力を自主的に積み重ねるようになります。
そのため、思想の浸透を「すべての社員が、期待される成果を自ら進んで積み上げていく状態」と定義している企業もあります。
結果として、離職率の低下や採用力の強化、組織全体のKPI改善など企業経営におけるさまざまな成果につながります。
インナーブランディングとアウターブランディングの違い
インナーブランディングとアウターブランディングは、どちらもブランドを強化するための重要な活動です。ただし、対象とするオーディエンスが異なります。
アウターブランディングは、主に顧客や投資家などの社外の人たちに向けて行うブランディング活動であり、商品やサービス、ブランドそのものの認知度向上や好意度の向上を目的としています。
代表的な例として、下記のような広報活動や、展示会出展などが挙げられます。
- 広告
- PR
- SNS
一方、インナーブランディングは従業員をはじめとした社内の人たちに向けて行うブランディング活動です。社員の共感と行動を引き出し、企業理念を組織内に浸透させることを目的としています。
インナーブランディングの目的
インナーブランディングの最も重要な目的は、企業理念や価値観の浸透を促進することです。ミッション、ビジョン、バリュー(MVV)などと呼ばれる企業理念は、企業戦略やブランド戦略の根幹を支える大黒柱です。
中長期的な成長を実現するには、全ての従業員が共通の目的意識を持ち、自らの意思で行動できる状態が理想ですが、企業理念は時とともに風化してしまうため、意図的に浸透施策を講じる必要があります。
また、インナーブランディングを進めていく中で理想的な状態として想定されるのが「一体感があり、活力のある組織」です。ブランドへの信頼感や帰属意識が強くなることで、組織の一体感が増し、変化への耐性を生み出します。
企業理念が浸透すれば自然と一体感が生まれると思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。
組織の文化や風土が理想的な状態でなければ、従業員が変化を嫌ったり、リスクを避ける判断をしがちになります。そのため、組織文化や風土は、理念の実現に向けて意図的に強化していく必要があります。
インナーブランディングの3つのメリット

インナーブランディングを進めることにより、企業は以下の3つのメリットを享受できます。
従業員のやる気を高められるため離職を防げる
インナーブランディングは、従業員のやる気を高められるため、離職を防げます。自社の価値観に共感した従業員は自発的に行動してくれるため、企業が求めていることを「やらされている」のではなく「やりたい」の状態で実行してくれます。
前向きな気持ちで取り組めると成長曲線も緩やかになりますが、逆に消極的な気持ちで取り組むと成長曲線が急激になりますので、企業としては前者の状態を作ることが重要です。
社内外に一貫したブランドイメージを伝えられる
インナーブランディングに取り組めば、社内外に一貫したブランドイメージを伝えられます。
従業員がブランドの価値やビジョンを正しく理解し、それを日々の業務や対外的な接点で自然に表現できるようになることで、社内の意識が統一され外部にも一貫性のあるメッセージが届くようになります。
ただし、企業の理想像と現場の実態にギャップがあると、従業員の理解や行動にズレが生じ、ブランドイメージにもばらつきが出てしまいます。
そのため、理想を掲げるだけでなく実際の組織の状況や従業員の声を反映しながら、ブランドの方向性を現実に即したものとして見直していくことも大切です。
組織文化を強化でき企業の競争力を高められる
インナーブランディングに取り組めば、組織文化を強化でき、企業の競争力を高められます。ブランド理念を実現するためには、まず従業員が企業の価値観を共有することが基本となり、これが組織文化の土台となります。
しかし、価値観を共有するだけでは十分ではありません。従業員がその価値観に基づいて自発的に行動する「行動の自律」と、経営陣や人事が価値観に沿った行動を促し続ける「行動の管理」の両方が必要です。
このバランスが取れて初めて、価値観が組織の中に根づき、強い文化が形成されていきます。
強固な組織文化が育つと、従業員一人ひとりの判断や行動が企業の目指す方向と自然に一致し、部署間でも前向きな競争が生まれます。その結果、組織全体のパフォーマンスが高まり、企業としての競争力も向上していきます。
インナーブランディングで注意すべき3つのポイント
インナーブランディングは、良い取り組みである一方、いくつか注意すべきポイントがあります。
ここでは、インナーブランディングで注意すべきポイントについて紹介します。
多くのリソースが必要になる
インナーブランディングの成功には、社内に価値観を浸透させるための継続的な施策が欠かせません。価値観を浸透させるための施策には、定期的な社内報の発行や社内イベントの開催など、さまざまなものがあります。
ただし、これらの施策は一度に導入できるものではなく、段階的に進める必要があるため、数年単位の計画が求められると言われています。そのため、ブランディング担当チームだけでなく、経営層や各部署の責任者による強いコミットメントが欠かせません。
また、各部署長のコミットメントがある状態でも、インナーブランディング担当チームが全ての施策を手掛けるのは非効率です。より効果的にブランド価値を浸透させるためには、インナーブランディング専用の予算を各部署に設け、各部署で独自性をもった施策を打っていくことが理想です。
一部の従業員から反発を招く可能性がある
インナーブランディングを進めていく中で、制度や施策の導入時に一部の従業員から反発を招く可能性があります。
例えば、VC制度などの新しい制度を導入した際「本当に必要なのか」「えこひいきではないか」といったネガティブな声が上がることがあります。
MVVやバリューがまだ十分に浸透していない段階で、社内にコンペティション文化を取り入れた結果「成果主義の文化が定着してしまうのではないか」という懸念が生まれることもあります。
そのため、インナーブランディングで仕組みを導入する際は浸透度やフェーズ感に配慮して、軸足をおくべきかどうかの判断が必要です。また、強いリーダーシップとエンゲージメントも必要になります。
短期間では成果が実感しにくい
インナーブランディングは、企業理念や価値観を浸透させる長期的な取り組みです。そのため、短期間では成果が実感しにくいことに注意が必要です。
一般的に、インナーブランディング施策の効果を実感し始めるには、1年〜2年程度の期間を要すると言われています。
「本当に浸透しているのか?」と不安になり、早期に施策の見直しを行うと逆効果に繋がります。成果が実感できなかったとしても、まずは継続していただきたいです。
インナーブランディングの進め方|5ステップ

インナーブランディングは、社内での根付きを意識して長期的に取り組む必要があるため、継続的に施策を実行していくことが重要です。
ここでは、インナーブランディングを進める上での「5つのステップ」を紹介します。
1.現状を可視化し、目指すゴールを設定する
インナーブランディングを進める上で「初期状態」と「理想状態」の2つの状態を明確にしておくことは重要です。そうすることで、それぞれの状態の差分を埋めていく施策を集中して実行することができるからです。
初期状態の可視化には「従業員エンゲージメント調査」がおすすめです。従業員エンゲージメントとは、従業員が業務や職場に対して感じている心理的な充足感のことを指します。
特に、理念共感度(会社の理念に対してどれだけ共感しているかを測る指標)と、離職意向(離職したいと思っているかを測る指標)は、理念の浸透具合を測る上で重要な指標です。
理想状態の設定には「OKR」という目標管理手法をおすすめしています。OKRは、目標の設定と進捗の共有を習慣化することで、組織におけるエンゲージメントの向上を促すことが出来るため、理想状態の設定に適しています。
2.ミッション・ビジョン・バリューを言語化する
ここまでで設定したゴールや理想的な状態を踏まえ、目指すブランドの理想像を言語化します。言語化するのは、「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」です。
ミッション・ビジョン・バリューの定義は、下記の通りです。
- ミッション(Mission)......企業が存在する目的(価値を提供している社会課題)
- ビジョン(Vision)......ミッションを達成するために企業が追い続けている理想の姿(5年後に実現できている状態)
- バリュー(Value)......ビジョンを実現するために社員一人ひとりが大切にしている価値観(実際の行動指針)
ここで重要なのは、企業が目指している理想的な姿ではなく、時代背景や競争環境を踏まえたうえで、実現可能性の高い姿を作成することです。また、バリューは全社的に共通のものを掲げるだけでなく、各部署ごとにローカライズすることをおすすめします。
3.価値観を伝える仕組みを整備する
価値観を伝える仕組みを整備することが、価値観を浸透させていく上で非常に重要です。
日本企業でも、理念やバリューを浸透させるために、さまざまな取り組みが行われています。よくあるのが「海外企業で浸透レベルが高い〇〇を参考にし、次のような施策を行いました」といった形でプロジェクトが始まるケースです。
しかし、従業員にとって「努力を求められる価値観の浸透」ではなく「楽しみながら継続的に体験できる価値観の浸透」のほうが、結果的に独自性のある文化を育みやすいと感じています。
言い換えると、理想的な価値観を作り上げていくのではなく、自然に体験していく方が効果的ということです。
従業員にとっての「楽しみ」とは、バリューアウォード(最も価値観に沿った行動をした従業員に対して表彰を行う制度)や、社内報に価値観に沿った行動をした従業員を紹介するコーナーなどがあります。
また、定期的に価値観のレビューを行い、時代に合わせて更新していくことも重要です。
4.ブランドの理解を深める教育機会を設ける
ブランド浸透を達成するために最も重要なのは、価値観上の判断を求められた際に、従業員がブランド戦略や理念を思い出してくれる状態を作ることです。
価値観を思い出してもらうには、それ以前に価値観を理解してもらっている必要があります。そこで重要なのが、教育機会の設計です。教育機会は目的別に設計し、社内教育のメインプログラムとして位置付けると効果的です。
また、内容は「ミッション → ビジョン → バリューシステム」の順番で学習することを推奨します。これにより、学習に対する前向きな期待感を醸成し、スムーズに価値観浸透へとつなげることができます。
社内教育の定番制度である「新入社員研修」や「中途社員歓迎会」などのタイミングで導入することで、より効果的にブランド浸透を進めていけるでしょう。また、「理念浸透推進者制度」などといった制度を設け、価値観を社内に広めていく文化づくりを進めることも効果的です。
5.施策の成果を評価し、改善を続けていく
ブランド理解度調査やエンゲージメント調査など、定期的に施策の成果を評価することが重要です。誇張表現ではありますが、全てのうまくいっている企業の裏には、失敗と改善の積み重ねがあります。
成功事例で紹介した企業に限った話ではなく、優れた企業文化を作り上げることは、実は非常に難易度の高いことなのです。少しずつ試行錯誤を繰り返しながら、理想のブランドに近づけていただければと思います。
参考:『ブランディング』成功の鍵を握る!?『インナーブランディング』 | 株式会社SBSマーケティング
インナーブランディングの成功事例

国内外問わず多くの成功事例がありますが、その中でも特に印象的な3事例を紹介します。
ブランドの軸を明確にし理念を浸透させて一体感を生み出す|東レエンジニアリング株式会社
東レエンジニアリングでは、理念やスローガンの浸透度合いを定期的に測定し、数値が目標に達しない場合は全社を挙げて浸透施策に取り組んでいます。
施策の内容は毎年変えながらも、カルチャーブックや社内ムービーなどを活用し、社員一人ひとりが理念を日常業務の中で自然に体現できるよう工夫されています。こうした取り組みにより、浸透度の数値は毎年着実に改善しています。
自社のアイデンティティや重視する価値観を明確に定義し、それを全社で一貫して共有・実行していることから、強く一貫性のあるブランドを構築しています。
外部の視点と挑戦文化を融合し、変革と成長を推進|小野薬品工業株式会社
小野薬品工業は、長期ビジョン実現に向けて、挑戦を重視する企業文化の醸成に取り組んでいます。
近年では、事業ポートフォリオの改革を進める中で「革新性」を評価基準の一つに加えるなど、変革の加速に向けた取り組みを強化しています。
その一環として、外部の専門性や知見を積極的に取り入れることで、社内に新たな視点を持ち込み、社員の意識変化を促しています。
従来の枠にとらわれない自由な発想が生まれやすい土壌が育ちつつあり、社内ビジネスコンテスト「HOPE」を通じて、自発的に革新的なアイデアを提案する動きも広がっています。
社員主導で企業文化をつくり、ブランドと働きがいを高める|株式会社LIFULL
株式会社LIFULLは「日本一働きがいのある会社」を目指して、社員一人ひとりが企業文化やブランドの創造に参加するインナーブランディング戦略を実践しています。
社名を「LIFULL」に変更し、企業メッセージを「あらゆるLIFEを、FULLに。」に統一することで、ブランドの一貫性を保ちつつ、社内外への認知度向上も図っています。
また、社員の提案をもとに中古ビルをリノベーションし、本社オフィスへ移転しました。オフィスのコンセプトには「ENGAWA(縁側)」を採用し、社内外の交流を促進する空間づくりを進めています。
さらに、有志の社員が参加する約20のワーキンググループを立ち上げ、ビジョンの体現や働き方の改善、育児や介護と仕事の両立支援など、多岐にわたるテーマに取り組んでいます。
こうした活動によって、社員の内発的な動機づけと当事者意識が高まり、自律的に行動する文化が根づいています。加えて「薩摩の教え」を参考にした挑戦を評価する仕組みも導入しており、社員が安心して新たなチャレンジに取り組める風土を築いています。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
私たち縁達磨は、商売繁盛の縁を引き起こす支援者であることを自負しています。
ビジョン(目指す理想の未来)である「失われた時代に終焉を告げる。 」を実現するために、ブランディングを軸に、下記のような幅広い領域で戦略的な支援を行っています。
- 商品開発支援
- プロモーション立案
- ブランド戦略立案
- 新規顧客獲得施策(デジタル広告)
- SNS運用
- コンテンツ制作
- キャスティング
- 海外市場参入
年々、ブランディングの重要性は高まっていますが、先進的な企業は「ブランドを守るための行動変容を起こす仕組みづくり」にまで踏み込んでいます。
弊社でも「縁起こしブランディング」と名付けて、思想に共感した価値あるクライアントのブランドを守るための行動変容を起こす仕組みづくりの支援を加速させています。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
ここまでインナーブランディングについて解説をしてきましたが「うちの会社でもインナーブランディングに取り組みたい」と思った方は、ぜひお気軽にご相談ください。
インナーブランディングは1年、2年で成果が出るものではなく、数年単位の長期的な取り組みです。少しでも成功の確率を高めるために、ぜひ弊社に相談してください。
お話を聞く中で提供できそうな価値があれば、弊社のサービスを紹介する形になるかと思いますが、価値を提供できないと判断した場合は、正直にお伝えしますので、ご安心ください。
少しでも興味を持っていただけましたら、お気軽にご連絡ください!
商売繁盛の縁を引き起こせるよう、一生懸命がんばります。
ご縁に感謝。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.