
2025.08.24
リブランディングとは?意味や成功事例などを簡単に解説!
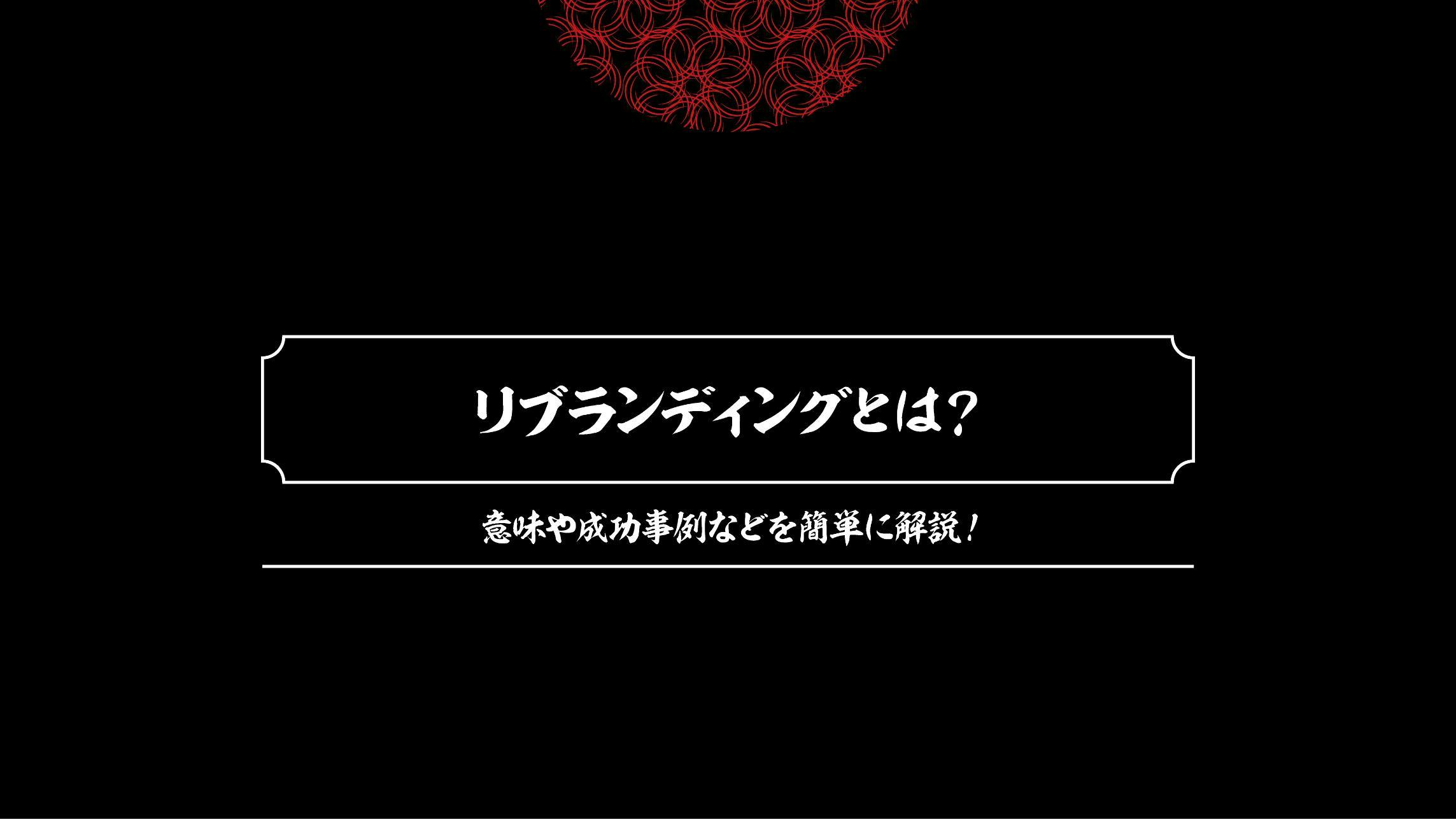
競争が激しく移り変わりの早い時代において、企業やブランドが成長を続けるには、環境の変化に応じた見直しが欠かせません。「顧客の反応が鈍くなっている」「新しい市場や顧客層にアプローチしたい」といった課題を抱えている方にとって、有効な手段となるのが「リブランディング」です。
この記事では、リブランディングの意味を簡単に紹介するとともに、具体的な進め方や成功事例などを解説します。
リブランディング(Rebranding)とは?

リブランディングとは、企業やブランドが既存のイメージや認知度を刷新するために行う再構築活動全般のことです。
言い換えれば、立ち上げからここまで積み重ねてきたブランドの歴史(=現在のブランドのポジション)を、より望ましい未来のポジションへと引き上げるために、一から作り直すようなイメージです。
リブランディングには、さまざまな施策が含まれます。例えば、下記の見直しや変更が挙げられます。
- ロゴ
- タグライン
- デザインルール
- 商品パッケージ
- ウェブサイト
- 商品・サービスの改廃
- ターゲット層の再設定 など
しかし、本質的に問われるのは「何を変えるか?」ではなく、「何を守るべきか?」という視点です。変化の中においても、企業の核となる価値や信念を見失わずに再定義していくことが、リブランディング成功の鍵となります。
また、企業やブランドが世の中で価値を発揮するには、何かしらの想いや理念を守り抜く必要があります。その想いや理念こそが、ブランドの核となるものです。
リブランディングを行う3つのメリット
リブランディングは、単なるロゴやデザインの変更に留まらず、ブランドの価値を再定義し、社会的な存在意義を再構築する取り組みです。新たな方向性を定めた後は、その価値を適切に伝えていく必要があります。
ここでは、リブランディングを行う「3つのメリット」を紹介します。
新たな市場や顧客層にアプローチできる
リブランディングは、既存のブランド資産を見直し、新たな価値を打ち出すことで、新しい市場や顧客層にアプローチする機会を生み出します。
例えば、これまでのブランドが特定の年代や志向に強く訴求していた場合でも、ブランドの方向性やターゲット設定を見直すことで、これまでリーチできていなかった層に届けられる可能性があります。
そのため、単に見た目やロゴを変えるだけでなく、ブランドの根本にある価値や伝えたい世界観を再定義し、下記などを総合的に調整することが重要です。
- 商品
- サービス
- メッセージ
- チャネル
リブランディングを通じて既存のブランドイメージから脱却することで、新しい顧客にとっての「選ばれる理由」を創出でき、これまでアプローチできなかった市場に扉を開くことが可能です。
社内外に一貫した価値観を共有できる
リブランディングは、企業が大切にする価値観を社内外で一貫して共有する絶好の機会です。
事業環境や市場の変化が激しい時代において、価値観に共感した顧客や従業員との強固な関係は、企業の持続的な成長に直結します。特に、価値観に共鳴して集まった顧客(支持層/コアファン)は、ブランドに対して高い忠誠心を持ち、自らその魅力を発信する存在になります。
これにより、口コミやSNSなどを通じた「共感の拡散(バイラル効果)」が生まれ、新たな顧客層にも価値観が伝わりやすくなります。
こうした支持層を育てるには、企業の価値観が社内外でズレなく伝わっていることが重要です。開発、販売、マーケティングなど、すべての接点で「この企業らしさ」が一貫して伝わることで、ブランド全体の信頼性が高まります。
そのため、価値観の再定義や再設計は、リブランディングの重要なプロセスとして多くの企業で取り入れられています。企業の内と外、どちらにも軸を共有できてはじめて、強いブランドが成立するといえるでしょう。
最適なターゲットを明確にできる
リブランディングは、企業やブランドが「誰に、どんな価値を届けたいのか」を改めて見つめ直す機会になります。
ブランドの方向性や世界観を再定義することで、それにふさわしいターゲット像も自然と明確になっていきます。
このプロセスでは、これまで漠然としていた対象顧客を、具体的な人物像やニーズレベルに落とし込むことが可能です。例えば、年齢や性別だけでなく、価値観やライフスタイル、購入動機などの視点から細かく定義することで「本当に届けたい相手」が明確になります。
一部では「ターゲットが狭まりすぎるのではないか」という懸念もありますが、実際には適切に絞り込まれたターゲットの方が、商品やサービスの訴求が伝わりやすく、広告効果やブランドの好感度も高まりやすくなります。
リブランディングによって最適なターゲットを定義できれば、その後のマーケティングやプロダクト開発の意思決定も一貫性を保ちやすくなり、ブランド全体の成果につながります。
リブランディングを行う方法

リブランディングを行う方法はいくつかありますが、大きく分けて「ブランド再構築」「価値の再定義」「方向性の再確認」の3つに分類できます。
それぞれの手法について解説します。
ロゴやデザインを見直してブランドを再構築する
ロゴやデザインは、ブランドの世界観や価値観を視覚的に表現する重要な要素です。そのため、リブランディングにおいても最初に見直されることが多い領域です。
ただし「パーパス」や「ミッション・ビジョン・バリュー」といったブランドの本質的な価値観や、ターゲット市場・顧客層を十分に見直さずにロゴやデザインだけを変更してしまうと、後から価値観とのズレが生じる可能性があるということです。
デザインと中身が噛み合わないまま刷新を行えば「表層だけ変えた印象」や「他社の模倣」と受け取られるリスクも高まります。
一方、すでに価値観が明確で社内外に浸透している状態であれば、ロゴやデザインだけの見直しでも、ブランドの印象を効果的に再構築できる場合があります。
ブランドの中身と外見の整合性を意識したうえで、どこまで手を加えるべきかを判断することが、リブランディング成功の鍵となります。
スローガンやコピーを見直して価値を正しく伝える
リブランディングによってターゲット層が変わったり広がったりする場合、ブランドが届けたい価値を正しく伝えるための「言葉の再設計」が欠かせません。その中心となるのが、スローガンやコピーの見直しです。
スローガンやコピーは、ブランドと出会う最初の接点であり、第一印象を左右する重要な要素です。魅力的な言葉が使われていれば、商品やサービスに対する関心が高まり、ブランド全体の印象もポジティブになります。
また、スローガンやコピーは単なる装飾ではなく、ブランドのコンセプトやターゲット、提供価値と整合性を取る必要があります。そのため、コピーライティングはブランド戦略の終盤で設計するのが理想です。
さらに、SNS時代においては、広告に使わなくても強い言葉が共感や拡散を呼ぶこともあり、ブランドの認知や印象形成に大きな影響を与えます。価値を的確に、かつ魅力的に伝えるためにも、スローガンやコピーには十分な検討が必要です。
組織内外の意見を取り入れてブランドの方向性を見直す
経営理念やブランドのコアバリューなど、ブランドの根幹にあたる部分は大きく変える必要はありませんが、手段やステートメントなどは柔軟に見直す必要があります。ここで重要なのが「強度の高い仮説」です。
強度の高い仮説があればあるほど、新しいブランドの方向性に対する説得力を高めることができ、新ブランドの方向性や価値支給方法に対する改良サイクルを早められます。
リブランディングの進め方|3ステップ

リブランディングを進めるには前のブランドを解体し、新しいブランドを再構築する工数が必要です。
ここでは、リブランディングを進める上で欠かせない3つのステップを紹介します。
ブランドの現状と課題を洗い出す
リブランディングを成功させるためには、現在のブランドの立ち位置を正確に把握し、どこに課題があるのかを明確にすることが重要です。そのため、最初のステップでは、ブランドを取り巻く環境や評価を多角的に分析し、強み・弱みを特定していきます。
特に重要なのは「何が課題なのか」を見極めることです。課題が曖昧なままでは、方向性を誤ったリブランディングになりかねません。
分析には、以下の2つの視点を組み合わせることが効果的です。
- 定性的分析......消費者・代理店・社員・経営層など、社内外のステークホルダーへのインタビューを通じて、ブランドに対する認識や期待値を把握します。
- 定量的分析......ブランドの認知度やイメージ、好感度などを数値で可視化する「ブランド・ヘルス・モニタリング」を活用します。
両者を併用しても意見が一致しない場合は、仮説を一度棚上げし、追加の調査やヒアリングを重ねて検証を繰り返すことが重要です。こうして徹底的に現状を見つめ直すことで、リブランディングの土台が固まります。
新しいブランドの方向性を定める
リブランディングの成功には、これから目指すべき「新しいブランドの姿」を明確に定義することが欠かせません。これは単なるイメージ作りではなく、ブランドのありたい姿=ゴールを設定することであり、ブランド活動全体の指針となります。
このゴール設定にはさまざまな手法がありますが、中でもブランドの価値や構造を言語化・視覚化するために有効なのが、次の2つです。
- ブランドバリュー......ブランドが顧客に提供する価値や、社会に対して果たす役割を明文化する手法。ブランドの本質を言葉に落とし込むことで、社内外の共通理解を促す。
- ブランドピラミッド......機能的価値から情緒的価値、ブランドの本質的な信念までを階層構造で整理するフレーム。ブランドの核となる思想や態度を段階的に可視化できる。
新しいブランドの価値を社内外に広める
ステップ2で定めたブランドビジョンやブランドバリューは、策定して終わりではありません。社内外にしっかりと浸透させることで、はじめてブランドの価値が現実のものとして機能し始めます。
社内に対しては、ブランドバリューに基づいた行動指針や評価制度を設計し、従業員一人ひとりが自分ごととしてブランドを体現できる環境を整えることが重要です。経営層から現場まで、一貫したメッセージを届けることが浸透の鍵となります。
社外に対しては、ブランドの価値や世界観をわかりやすく伝えるコンテンツを通じて、ステークホルダーとの接点を設計していきます。広告、SNS、ウェブサイト、PRなどあらゆるチャネルで「新しいブランドらしさ」を表現することで、共感と信頼を生み出します。
このように、社内外への戦略的な浸透活動を通じて、ブランドの価値を定着させ、持続的に支持されるブランドへと育てていきましょう。
参考:SNS集客で結果を出す方法とは?運用のコツと事例、サービス比較5選|株式会社Epace(イーペース)
リブランディングの成功事例

リブランディングを成功させるためには、生活者や社内の声を丁寧に聞き、新しいブランドの指針を策定することが重要です。
ここでは、リブランディングの成功事例を3つ紹介します。
社内理解から一体感を築く|祇園辻利
創業1838年の京都の老舗宇治茶ブランド・祇園辻利は、リブランディングを実施するにあたり、まず社内の理解と一体感の醸成に注力しました。
背景には、マーケティング課新設時に起きた部門間の認識ギャップがあります。営業部門との間に業務理解の差が生まれ、社内に壁ができてしまったのです。
このような状態では、ブランドが社内に浸透せず、外部に一貫したメッセージを届けることも難しいと判断されました。
そこで同社は、インナーブランディングを通じて社員の理解を深め、ブランドへの共感と主体性を育てていきました。社員一人ひとりがブランドの方向性を「自分ごと」として捉え、部門を越えて協力し合う文化が社内に根づき始めています。
外部に向けた取り組みとしては、ブランドデザインの統一やウェブサイトの再構築を実施。祇園辻利と茶寮都路里が同じ企業であることを明確に伝えることで、ブランド全体の一体感を高めました。
その結果、祇園辻利は抹茶専門店という枠を超え、上質な体験を提供する高級茶房としてのブランドイメージを確立しつつあります。
健康総合ブランドへと進化する|タニタ
タニタは、体重計や体組成計などの測定機器メーカーとして知られてきましたが、従来の枠を超えた「健康総合ブランド」への進化を進めています。
その転機となったのが、2012年に開設された「丸の内タニタ食堂」です。高栄養・低カロリーをコンセプトにしたこの社員食堂スタイルの店舗は、メディアでも大きな注目を集め、同名のレシピ本や関連商品のヒットにつながりました。
これにより「測る」だけでなく「整える」「支える」健康支援のイメージを確立することに成功しました。
このように、タニタは「人々の健康づくりに貢献する」という社会的意義を見つめ直し、体組成計メーカーから健康支援企業へとブランドを再構築しました。
自社の強みを拡張しながら、社会的価値の高い分野での存在感を高めている点が、タニタのリブランディング成功の大きなポイントです。
ブランドの統一と未来志向の改革を実現する|ヤンマー
ヤンマーは1912年に創業し、農業機械メーカーとして日本の農業を支えてきました。2013年に創業100周年を迎えるにあたり、ブランドイメージの再構築を目的としたリブランディングに着手しました。その背景には、欧米では「船舶用エンジンブランド」、国内では「農機具メーカー」として異なるイメージが定着していたという課題がありました。
リブランディングでは、ロゴやコーポレートカラーの統一に加えて、農作業用ウェアやトラクターのデザインも一新しました。これにより、ヤンマーは「グローバルで統一されたブランド」としての印象を強め、国際市場における競争力を高めることに成功しました。
さらに、ヤンマーは「持続可能な未来の実現」を目指す企業としての姿勢も明確に打ち出しました。食料生産とエネルギーの分野において、環境に配慮した技術やソリューションを提供する企業へと進化し、農業機械メーカーという枠を超えて、新たな価値の創出に挑戦しています。
ヤンマーは、ブランドの統一によって発信力を高めると同時に、未来志向の戦略によって企業のビジョンをより明確にし、リブランディングを通じて世界的なブランド価値を築き上げました。
縁達磨では縁起こしブランディングで商売繁盛を支援
縁達磨では「縁起こしブランディング」を軸とし、リブランディングを通じて商売繁盛を支援しています。ただ見た目を変えるのではなく、ブランドのビジョンと生活者に提供すべき価値を結ぶように情報設計を行うのが特徴です。
この「縁起こしブランディング」は、「心・敵・技・体・動」の5工程からなる独自のブランド戦略の手法です。足元の販売効率を高めつつ、将来的な競争力を育てることを目的としています。
商売のお悩みはいつでもご相談ください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
縁達磨では、リブランディングを軸に幅広い支援を行なっています。少しでもご興味を持っていただけた方は、こちらからお気軽にご相談ください。
商売繁盛の縁を引き起こせるよう、一生懸命がんばります。
ご縁に感謝。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.