
2025.07.12
CIデザインとは?導入目的や開発プロセス、成功事例も紹介
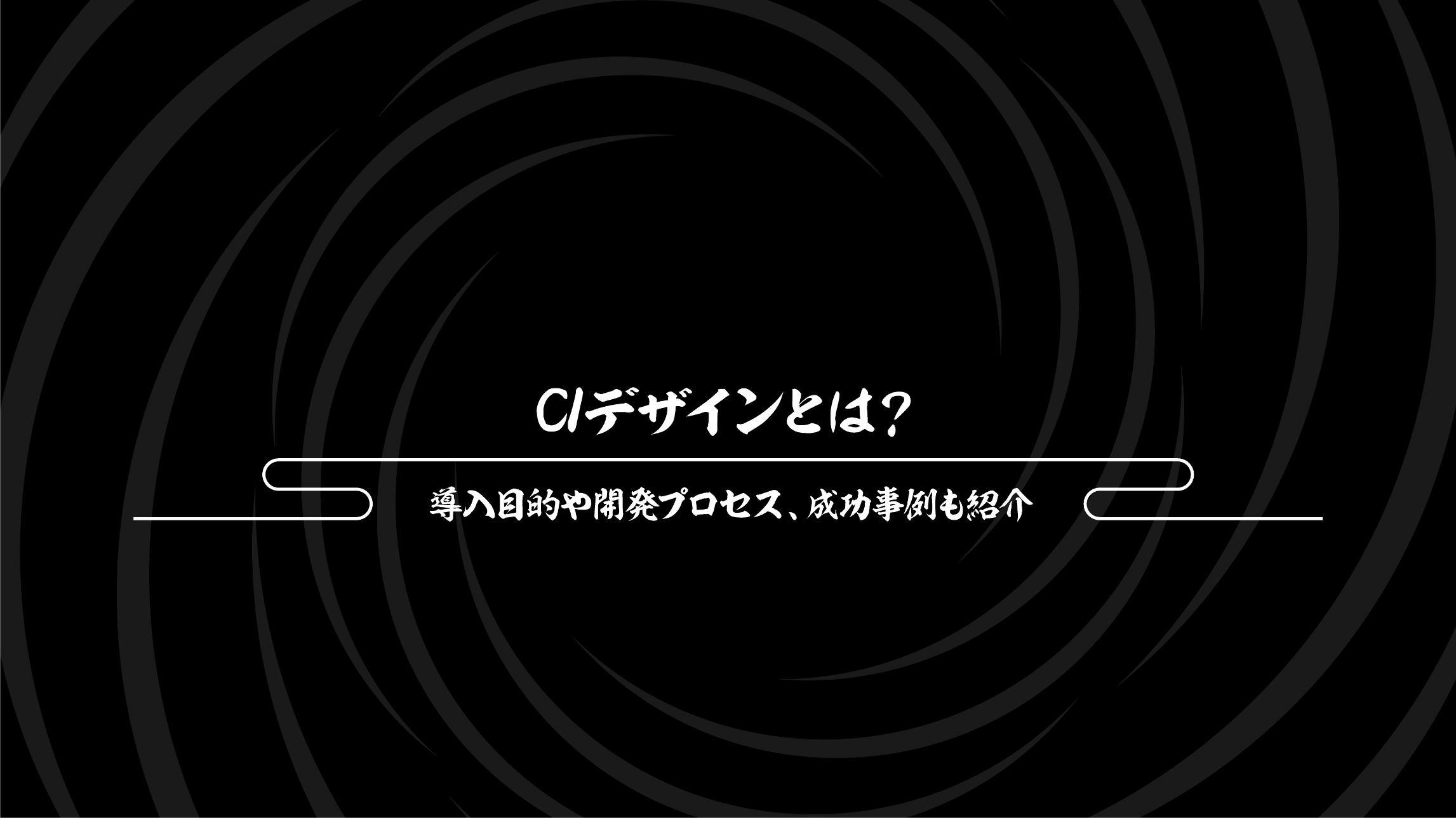
企業のイメージを内外に伝えるために欠かせないのが「CI(コーポレート・アイデンティティ)デザイン」です。ロゴやカラー、フォントなどを通じて、企業の理念や価値観を視覚的に表現することで、ブランド認知や信頼性の向上につながります。
本記事では、CIデザインの基本的な考え方から、VIデザインとの違い、導入する目的、構成要素、開発のステップ、さらに実際の成功事例まで、わかりやすく解説します。
CI( Corporate Identity )とは?

CI(Corporate Identity)とは、企業の理念や価値観を視覚的に表現し、社内外に一貫したメッセージを伝えるための戦略です。ロゴ、カラー、フォント、デザインのトーンなどの要素を通じて、企業の個性や方向性を明確に示します。
CIは単なるデザインではなく、企業の存在意義やビジョンを反映した「ブランドの核」です。例えば、自社の文化や考え方を視覚的に表現することで、顧客との感情的な共感を生み出し、信頼や親しみを育てる効果があります。このようなつながりは、競合との差別化やブランドロイヤルティの向上につながります。
また、CIは固定されたものではなく、企業の成長や市場環境の変化に応じて見直すべき資産です。時代に合ったデザインやメッセージへと更新することで、常に新鮮で魅力的なブランドイメージを保つことができます。CIは、企業の持続的な競争力を支える戦略的基盤といえるでしょう。
CIデザインとVIデザインの違い

CIデザイン(コーポレート・アイデンティティデザイン)とVIデザイン(ビジュアル・アイデンティティデザイン)は、どちらも企業のブランド形成に関わる重要な手法ですが、役割と範囲が異なります。
CIデザインは、企業の理念や価値観をもとに、組織全体の「あり方」や「方向性」を視覚的に表現するものです。ロゴやカラー、フォントなどのビジュアル要素を通じて、企業の一貫したメッセージや個性を伝え、ブランドの信頼性や存在感を高める役割を果たします。
一方、VIデザインは、CIの一部として機能する視覚表現に特化した手法です。ロゴや色使い、書体などの具体的なデザイン要素を整え、視覚的に統一された印象を与えることを目的としています。VIは、見る人に企業イメージを直感的に伝える「見た目の設計」といえます。
つまり、CIデザインはブランドの「土台」を築く全体戦略であり、VIデザインはその戦略を視覚的に具現化する「表現手段」です。両者を組み合わせることで、企業は内外に一貫性のあるブランドイメージを確立できます。
CIデザインを導入する目的
CIデザインを導入する目的は多岐にわたりますが、主にブランド認知の向上、企業のアイデンティティの明確化、そして統一されたブランドイメージの構築が挙げられます。これらの目的を達成することで、企業は市場での存在感を強化し、顧客との信頼関係を築くことができます。
ここでは、CIデザインを導入する目的について紹介します。
ブランド認知を高めて市場での存在感を強化するため
CIデザインを導入する目的の一つは、ブランドの認知度を高め、市場での競争力を強化することです。商品やサービスがあふれる中で、企業が選ばれるには、自社の特徴や価値を明確に伝える必要があります。
ロゴやカラー、フォントといった視覚要素を統一することで、企業のイメージが視覚的に定着し、他社との差別化が図れます。例えば、特定の色や形が企業名と結びつくようになれば、消費者の記憶に残りやすくなり、選択の際に優位に働きます。
さらに、ブランドの認知が進めば、信頼感が生まれ、継続的な利用や口コミによる広がりも期待できます。CIデザインは単なる見た目の整備ではなく、顧客との接点を強化し、長期的な事業成長を支える重要な施策といえます。
企業の「らしさ」を明確にし、ブランドの軸を築くため
CIデザインを導入する目的の一つは、企業の「らしさ」を可視化し、ブランドの軸を明確にすることです。ここでいう「らしさ」とは、企業が大切にする価値観や文化、理念などを指し、それらを視覚的に表現することで、他社とは異なる独自の印象を形成できます。
例えば、環境保護を重視する企業であれば、ナチュラルな色合いや柔らかいフォントを用いることで、その姿勢を自然に伝えることができます。CIデザインは、こうした理念をデザインに落とし込み、一貫したメッセージとして社内外に届ける役割を担います。
「らしさ」が明確になると、顧客もその企業がどのような価値を提供しているかを直感的に理解しやすくなり、信頼の獲得につながります。結果として、競合が多い市場においても自社の立ち位置を明確にし、継続的なブランド成長を支える基盤となります。
統一されたブランドイメージ組織と顧客をつなぐため
CIデザインを導入する目的のひとつは、企業のあらゆる接点で統一されたブランドイメージを築き、社内と顧客の意識をつなぐことです。ロゴやカラー、フォントなどの視覚要素に一貫性があることで、企業の理念や価値観が明確に伝わり、顧客の信頼や認知を得やすくなります。
統一感のあるデザインは、広告・Webサイト・パッケージなどのあらゆるタッチポイントでブランドを識別しやすくし、印象のブレを防ぎます。また、社内においてもブランドの方向性が共有されやすくなり、社員の意識や行動の統一にもつながります。
結果として、顧客は企業に対して一貫性と安心感を抱き、ブランドへの信頼が高まります。これはリピーターの増加や口コミによる拡散にも効果を発揮し、企業と顧客の持続的な関係構築を支える基盤となります。
CIデザインに欠かせない4つの基本要素

CIデザインを構成する基本要素は、企業のアイデンティティを視覚的に表現するために非常に重要です。ここでは、CIデザインに欠かせない4つの基本要素について詳しく解説します。
ロゴ
ロゴは、CIデザインにおける中核的な要素であり、企業の「顔」としてブランドの認知や印象形成に直結します。名刺やウェブサイト、広告など多様な媒体で使用されるため、一貫性のある設計が不可欠です。
効果的なロゴは、視覚的なインパクトだけでなく、企業の理念や価値観を簡潔に伝える役割も果たします。たとえば、配色や形状、フォントの選定は、信頼感・革新性・親しみやすさといった印象を左右し、ブランドの個性を強調します。
ロゴは時代の変化に合わせてデザインを見直すことがありますが、根底にあるブランドのコンセプトやアイデンティティは一貫して保つことが重要です。
また、顧客がロゴを見たときに信頼や安心感を抱けるよう、シンプルかつ意味のあるデザインである必要があります。
カラー
カラーは、CIデザインにおいて企業の印象や価値観を視覚的に伝える重要な要素です。色には感情を喚起し、ブランドの個性や理念を直感的に伝える力があります。
例えば、青は信頼や安定を連想させ、金融やIT企業に多く使われます。赤は情熱や活力を表現し、飲食やエンタメ分野でよく採用されます。このように、色の選択は業種やブランド戦略、ターゲット層に密接に関わっています。
また、統一されたカラーはブランド認知を高める効果があります。広告やウェブサイトなど、あらゆる媒体で同じ色を使用することで、顧客に一貫性のある印象を与え、記憶にも残りやすくなります。
色は単なる装飾ではなく、企業のメッセージや価値を視覚的に強化する戦略的ツールです。CIデザインを検討する際は、ブランドの方向性に沿った色の選定と使い方が不可欠です。
フォント
フォントは、CIデザインにおいてブランドの印象やメッセージを視覚的に伝える重要な要素です。フォントの種類や太さ、間隔などのデザイン要素は、企業の個性や価値観を反映し、見る人の印象を大きく左右します。
例えば、信頼性や堅実さを伝えたい企業にはセリフ体、親しみやすさや柔らかさを表現したい場合にはサンセリフ体や手書き風のフォントが適しています。このように、フォントは企業の「らしさ」を視覚化する手段として機能します。
また、フォントの一貫性も重要です。名刺やウェブサイト、広告などすべての媒体で同じフォントを使用することで、ブランド全体に統一感が生まれ、認知度や信頼性の向上につながります。
さらに、可読性も忘れてはならないポイントです。特にデジタル上では、視認性の高いフォントを選ぶことで情報伝達がスムーズになり、顧客との円滑なコミュニケーションを支えます。
写真
写真は、CIデザインにおいて企業の価値やメッセージを直感的に伝える強力な手段です。適切な写真は、ブランドイメージの強化や顧客との感情的なつながりの構築に貢献します。
企業活動や製品の利用シーン、スタッフの働く姿などを写した写真は、企業の信頼性や親近感を高める効果があります。また、理念や文化が反映された写真を用いることで、企業の「らしさ」を視覚的に表現することができます。
写真のスタイルやトーンも重要です。明るく活気のある写真は開放的な印象を与え、落ち着いた色調の写真は高級感や信頼感を演出します。ブランドのポジションやターゲット層に応じて、表現を使い分けることが求められます。
さらに、CI全体との一貫性も意識すべきポイントです。写真の色味や構図、質感を揃えることで、ブランドとしての統一感が生まれ、顧客に対して明確で信頼性のある印象を与えることができます。
CIデザインの開発プロセス
CIデザインの開発プロセスは、企業のアイデンティティを確立し、ブランドを効果的に伝えるための重要なステップです。このプロセスは、企業の特性や市場のニーズを理解し、視覚的な要素を通じて一貫したメッセージを発信することを目的としています。
ここでは、CIデザインの開発プロセスを6つのステップに分けて紹介します。
1.現状調査と分析|今の会社の特徴や強みをしっかり調べる
CIデザインの第一歩は、企業の現状を正確に把握することです。企業の歴史、文化、ビジョン、ミッション、現在の市場での立ち位置などを整理し、ブランドの土台を明確にします。
社内インタビューやワークショップを通じて、企業の価値観や方向性を掘り下げると同時に、社員の認識とのズレがないかも確認します。これにより、企業が社会にどう見られたいのか、その核となるメッセージを定義する準備が整います。
あわせて競合分析も実施し、他社のCIやブランド戦略を比較することで、自社の差別化ポイントを見出します。さらに、顧客からの評価や期待を把握することも重要です。アンケートやレビュー、SNSの声などを通じて、企業に対するリアルな印象を反映させます。
これらの情報をもとに、自社の強みや課題を客観的に把握し、CI設計の方向性を定めていきます。
2.ブランドコンセプトの策定|どんな会社に見られたいかをはっきりさせる
ブランドコンセプトの策定は、CIデザイン全体の方向性を決める核となる工程です。企業がどのように見られたいか、どんな価値を誰に届けるのかを明確にすることで、伝えるべきメッセージが定まります。
まず、企業のミッションやビジョンをもとに、ターゲットとする顧客像を具体化します。顧客のニーズや期待にどう応えるかを整理することで、ブランドが提供すべき価値の輪郭が見えてきます。同時に、競合との違いを分析し、自社の強みや独自性を明確にします。
このプロセスを通じて、企業の「らしさ」やポジショニングが言語化され、ブランドの軸が形成されます。そしてこのコンセプトが、ロゴやカラー、フォントといったCIデザインの各要素に落とし込まれ、視覚的に表現されることになります。
ブランドコンセプトが曖昧なままでは、CI全体に一貫性が生まれません。明確なコンセプトをもとに設計を進めることで、社内外にぶれのないブランドイメージを伝えることが可能になります。
3.デザイン開発|見ただけで「この会社だ」とわかる工夫をする
デザイン開発は、ブランドコンセプトを視覚的に具体化する重要な工程です。ロゴ、カラー、フォント、写真といった要素を統一感を持って設計し、企業の個性を明確に伝えるデザインを構築します。
ロゴは企業の象徴となるため、理念や価値観を反映した形状や色を用い、視覚的に記憶に残るデザインが求められます。顧客がロゴを見ただけで企業を連想できる状態を目指します。
フォントの選定も、ブランドイメージに直結します。たとえば、堅実さを重視する企業にはセリフ体、先進性を打ち出したい場合にはサンセリフ体など、フォントが伝える印象を活用してブランドの「声」を整えます。
さらに、写真やビジュアル素材は、企業の世界観や活動を視覚的に語るツールです。製品やサービスの魅力を的確に伝える写真を使うことで、ブランドストーリーに説得力が生まれます。
これらの要素を一貫した方針で設計することで、「見ただけでその企業とわかる」ブランドイメージが構築されます。デザイン開発は、単なる装飾ではなく、企業のアイデンティティを視覚で表現する戦略的なプロセスです。
4.コミュニケーション方針の策定| 社員や顧客にどう伝えるかを考える
CIデザインを機能させるには、企業のブランドメッセージを社内外にどう伝えるかを明確にする必要があります。これが「コミュニケーション方針の策定」です。
まず社内に向けては、CIの目的や意義を全社員に共有することが重要です。研修やワークショップを通じてブランドの価値観やビジョンを浸透させることで、社員一人ひとりがブランドを体現する行動を取れるようになります。社内での理解が深まれば、ブランドイメージに一貫性が生まれます。
一方、社外に対しては広告・ウェブサイト・SNSなどの媒体を通じて、ブランドのストーリーや理念を分かりやすく伝えることが求められます。ロゴやカラー、言葉遣いなどを統一し、どの接点でも同じ印象を与えることで、ブランド認知と信頼性を高めることができます。
5.実行計画の立案|具体的なスケジュールと準備を進める
CIデザインを円滑に導入するためには、実行計画を明確に立てることが不可欠です。ここでは、プロジェクト全体の流れを整理し、実施に向けた具体的なスケジュールや準備内容を確定します。
まず、ロゴやツールの展開時期、社内説明、外部発信など、各ステップのタイムラインを設計し、タスクごとの進行状況を管理できる体制を整えます。これにより、関係者間での認識のズレを防ぎ、スムーズな実行が可能になります。
次に、必要なリソースを明確化します。デザイナーやマーケティング担当など、実務に関わる人材の確保、印刷やシステム更新にかかる予算の見積もり、外部パートナーとの調整など、実施に必要な要素を具体的に洗い出します。
また、情報共有の方法や意思決定のルールなど、関係者間のコミュニケーション体制もあらかじめ設計しておくことが重要です。さらに、想定外の事態に備えたリスク管理体制や対応フローを準備しておくことで、計画通りにプロジェクトを進行しやすくなります。
6.実行と浸透活動|実際に使い始めて社内外に広めていく
CIデザインの最終段階は、策定したブランドイメージを社内外で運用し、定着させる「実行と浸透活動」です。ここでは、単に新しいデザインを導入するだけでなく、企業全体にその意義を理解させ、継続的に活用される環境を整えることが求められます。
まず社内では、社員がCIの理念や目的を理解し、自らの業務に反映できるようにすることが重要です。ガイドラインの配布や研修、ワークショップを通じて、CIが「自分ごと」として浸透する仕組みを構築します。これにより、ブランドの一貫性が現場レベルで担保されます。
一方、社外に対しては、CIを反映した広告やWebサイト、SNSなどのコンテンツを通じて、新しいブランドイメージを発信します。顧客接点ごとにメッセージとデザインを統一することで、ブランド認知と信頼を高めることが可能です。
あわせて、顧客からの反応を収集し、改善に生かすサイクルを持つことで、ブランドの精度と共感を高めることができます。
CIデザインの成功事例

CIデザインの導入は、多くの企業にとってブランドの再構築や認知度向上に寄与しています。ここでは、実際にCIデザインを成功させた企業の事例をいくつか紹介します。
【株式会社モニクル】ロゴ刷新でCIの変化をわかりやすく可視化
株式会社モニクルは、CI(コーポレート・アイデンティティ)の刷新を通じて、企業イメージの再構築を図りました。
特に印象的なのは、新旧のロゴを並べて掲載し、変更点を視覚的に比較できるようにした点です。この工夫により、ブランドイメージの変化が一目で伝わり、社内外の理解を促進しています。
あわせて、コーポレートサイトや名刺も新デザインに統一され、刷新後のブランドコンセプトが明確に表現されています。デザイン担当者によるコメントも紹介されており、CI変更に込めた意図や価値観が具体的に伝わります。
この事例は、視覚要素を活用してCIの変化を効果的に伝える好例であり、リブランディングにおける実践的な参考モデルといえるでしょう。
【データライブ株式会社】新しいCIで採用ブランディングを強化
データライブ株式会社は、CI(コーポレート・アイデンティティ)の刷新を通じて、採用ブランディングの強化に取り組みました。新しいCIは、企業の価値観や働く環境を視覚的に訴求し、求職者に魅力的な印象を与えることを目的としています。
特に注目すべきは、新オフィスや社員の写真を積極的に掲載した点です。社内の雰囲気や働く人の表情を見せることで、企業文化が直感的に伝わり、親しみやすさとリアリティを演出しています。また、デザイン面でも、統一感のあるビジュアルとメッセージにより、ブランドイメージの明確化に成功しています。
さらに、採用サイトへの導線にも工夫が見られ、CIの変更意図や企業のビジョンが求職者に伝わりやすい構成になっています。CIデザインを採用活動にうまく組み込むことで、企業の魅力と一貫性を高めた好事例といえるでしょう。
【株式会社ユーグレナ】企業理念を再構築し、ブランドイメージを一新
バイオベンチャーの株式会社ユーグレナは、創業15周年を機にCI(コーポレート・アイデンティティ)の大幅な刷新に取り組み、企業の理念と方向性を再定義しました。新たに策定した「ユーグレナ・フィロソフィー」は、同社の価値観を社内外に一貫して伝えるための基盤となっています。
このプロジェクトは、社内公募で集まった意見をもとに始動しました。「グループの一体感を高めたい」という提案がきっかけとなり、ブランドのあり方を見直す必要性が共有されました。それまで、キャッチコピーやスローガンが時期ごとに変わっていたことで、社員間での認識にもばらつきが生じていた背景があります。
当初はロゴの一部変更を想定していたものの、経営戦略・マーケティング・食品事業など各部門の責任者が議論を重ねた結果、CI全体の再構築に方針を広げました。ロゴは英語表記からカタカナに変更し、親しみやすさと視認性を高めました。特に、海外展開を見据えた設計として評価されています。
さらに、これまでのビジョンやスローガンを廃止し、「フィロソフィー」に一本化することで、企業としてのメッセージを明確に統一しました。この変更により、サステナビリティを軸としたブランドとしての立ち位置を強化し、将来的な事業の広がりにも対応できる体制を築いています。
戦略から実行までを一気通貫で商売繁盛支援
縁達磨では、ブランド戦略やマーケティング戦略立案などの上流工程から獲得施策の下流工程を自社で一気通貫で支援することで、足元の販売効率を上げながら、未来の競争力をタマける統合型マーケティング支援が強みです。
事業領域を特化させ、専門性を高めることが主流となっていますが、事業環境がますます複雑化する中で「商売繁盛の縁を引き起こす」という使命を遂行するためには、上流工程から下流工程までを全方位でご支援し、全体最適をしていく必要があると考えているため、このような体制を敷いています。
商売の悩みをいつでも気軽にご相談ください。
CIデザインは、企業の理念や価値観をロゴやカラーなどの視覚要素で表現し、ブランド認知や信頼性を高めるために欠かせない戦略です。現状分析から始まり、ブランドコンセプトの策定、デザイン開発、社内外への浸透までを丁寧に進めることで、一貫したブランドイメージが確立されます。
成功事例から学ぶことも、実践への大きなヒントになります。CIデザインは、企業の魅力を伝え、持続的な成長を支える強力な武器になるでしょう。
縁達磨では、世界的なブランドのブランディングを担当してきたクリエイターを中心に、「心•敵•技•体•動」からなる独自のブランディング手法でブランドの価値を定義し、中長期的な販売効率を上げるための強いブランド作りを得意としております。
少しでも縁達磨へ興味を持って頂けましたら、ぜひ気軽にご相談ください!
縁達磨でご支援できないと判断した場合でも、喜んで信頼できるパートナーをご紹介します。
商売繁盛の縁を引き起こせるよう、一生懸命がんばります。
ご縁に感謝。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.