
2025.07.12
新規事業の参入事例5選|参入分野の選び方や絞り込み方も紹介
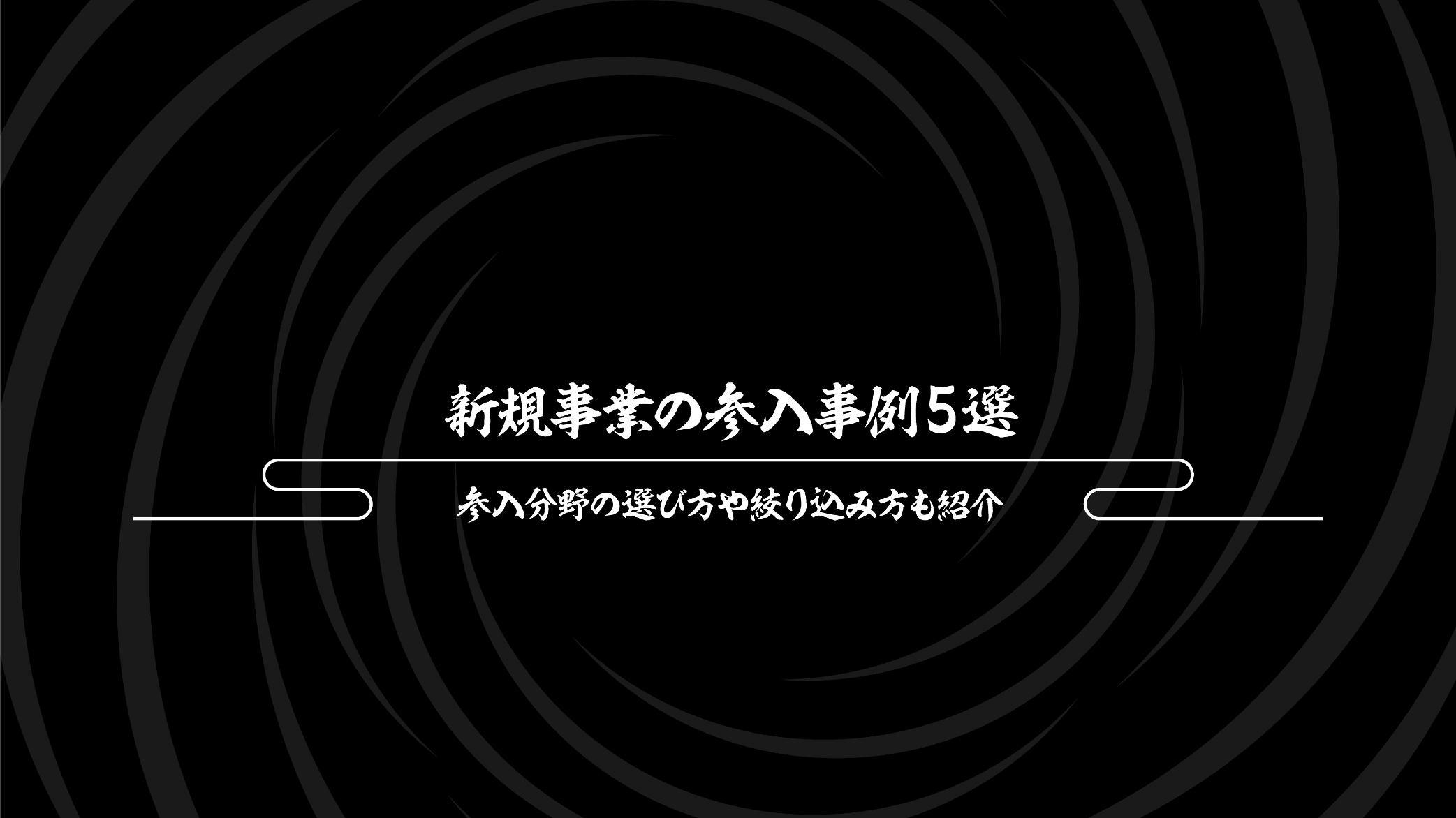
市場の変化や顧客ニーズの多様化に対応するうえで、企業にとって新規事業への参入は避けて通れない選択肢となっています。しかし、「どの分野に参入すべきか」「どうやって候補を絞り込むか」といった判断は簡単ではありません。
この記事では、新規事業の参入が求められる背景を解説するとともに、分野の選び方や判断基準、そして実際に成功している5つの企業事例を紹介します。
新規事業への参入はなぜ必要?

企業が新規事業に参入する最大の理由は、市場環境の変化に対応し、競争力を維持・強化するためです。
技術革新や顧客ニーズの多様化により、既存のビジネスモデルだけでは成長が頭打ちになるリスクが高まっています。新たな事業は、収益源の分散と成長の持続を可能にする重要な手段です。
また、新規事業はイノベーションを生み出す原動力でもあります。新しい技術や発想を取り入れることで、既存の製品やサービスを高度化でき、競合との差別化にもつながります。
さらに、新市場への進出により事業リスクを分散できる点も大きなメリットです。
加えて、環境問題や社会課題への対応も新規事業参入の背景にあります。企業には、持続可能な社会の実現に貢献する製品やサービスの提供が求められており、これに応えることでブランド価値や顧客からの信頼を高めることができます。
新規事業への参入は、環境変化に適応しながら企業価値を高めるための不可欠な戦略と言えるでしょう。
新規事業の参入分野の選び方

新規事業への参入を考える際、どの分野に進出するかは企業の成長に大きな影響を与える重要な決定です。適切な分野を選ぶことで、リスクを軽減し、成功の可能性を高めることができます。
ここでは、新規事業の参入分野の選び方についていくつかの戦略を紹介します。
既存事業の延長線上での展開戦略
新規事業への参入では、既存事業の延長線上での展開が効果的な手法の一つです。企業が保有するリソースやノウハウ、既存の顧客基盤を活用できるため、参入リスクを抑えながら確実に成果を狙えます。
例えば、現在提供している製品に関連した派生商品を開発したり、既存サービスに新機能を加えることで、新たなニーズに対応できます。製品特性を活かしたライン展開や、同一カテゴリ内での新製品投入は、既存顧客の満足度を高めると同時に、売上の拡大にもつながります。
さらに、すでに築かれた顧客との信頼関係があることで、新しい商品やサービスの導入時にも高い受容性が見込めます。この結果、マーケティングや営業にかかるコストを抑えながらスムーズな市場展開が可能になります。
社内資源を活かす再活用戦略
新規事業への参入では、社内資源の再活用が効果的な戦略となります。既存の設備、技術、人材、情報といったリソースを有効に使うことで、大きな追加投資を抑えつつ、新たな分野に展開できるのが特徴です。特に中小企業にとっては、限られた資源で成果を最大化する手段として有効です。
例えば、既存の製品や技術を改良し、異なる用途や市場に応用することが挙げられます。製造業であれば、生産ノウハウを転用して別ジャンルの商品を開発する、または既存のブランド信頼を活かして新サービスを立ち上げるといった展開が可能です。
さらに、社内の人材を新規事業にアサインすれば、専門知識や現場経験を即戦力として活用でき、立ち上げ段階からスムーズな運営が期待できます。社内資源の有効活用は、コストや時間の削減につながり、競争優位性の確立にも寄与します。
自社の強みを他分野に応用する横展開戦略
横展開戦略とは、自社が培ってきた技術やノウハウを異なる分野に応用し、新たな市場に参入するアプローチです。既存の事業で築いた強みを活かすため、ゼロからの立ち上げに比べて参入リスクを抑えながら新たな収益源を創出できます。
例えば、製造業の企業が高精度加工の技術を医療機器や環境機器の開発に転用するケースがあります。こうした展開では、既存の品質管理体制や技術者のスキルをそのまま活用できるため、立ち上げのスピードと品質の両立が可能です。
また、確立されたブランド力がある場合は、新しい分野でも顧客からの信頼を得やすく、市場への浸透もスムーズに進みます。社会的ニーズの高い分野へ進出することで、企業の成長と社会貢献を同時に実現できる点も魅力です。
自社の強みを他分野に応用する横展開は、経営資源の有効活用と中長期的な事業拡大を両立させる有力な戦略です。自社の技術や知見を改めて見直し、新たな価値を生む領域を見極めることが成功への第一歩となります。
成長市場を狙った参入戦略
新規事業を成功に導くには、成長が見込まれる市場への参入が効果的です。
成長市場とは、現在需要が拡大しており、今後も継続的な伸びが期待される分野を指します。こうした市場では競争が本格化する前にポジションを確立できるため、競争優位を築きやすくなります。
市場選定では、社会動向や技術革新、消費者の価値観の変化を分析することが重要です。例えば、脱炭素社会の実現に向けた政策が後押しする再生可能エネルギー分野や、健康志向の高まりによるヘルスケア・フードテック分野などは、典型的な成長市場といえます。
さらに、競合が少ないニッチ領域に早期参入することで、シェア獲得やブランドの定着が容易になります。ただし、需要拡大に伴い顧客の期待値も上がるため、製品やサービスの品質や対応力の向上は不可欠です。
新規事業の参入分野の候補を絞り込む5つの視点

新規事業への参入を検討する際、候補となる分野を絞り込むことは非常に重要です。適切な分野を選ぶことで、リスクを軽減し、成功の可能性を高めることができます。
ここでは、候補を絞り込むための5つの視点を紹介します。
市場性|顧客ニーズが存在するかを見極める
新規事業の成否を左右するのが、市場性の有無です。顧客ニーズが存在しなければ、どれだけ優れた商品やサービスでも市場で受け入れられません。まずは、ターゲット市場に「誰が、何を、なぜ求めているのか」を明確にすることが不可欠です。
そのためには、具体的な市場調査が必要です。アンケートやヒアリングを通じて顧客の課題や期待を把握し、どのような価値提供が求められているのかを見極めます。同時に、競合の提供価値や顧客評価を分析することで、差別化の方向性も明確になります。
また、消費者の嗜好や社会的な関心は常に変化しています。トレンドや規制、技術革新など、外部環境の変化を的確に捉え、柔軟に対応できる体制を整えることが重要です。市場の成長タイミングを逃さず、ニーズに合った商品をタイムリーに投入することで、競争優位を築くことができます。
収益性|利益を出せるビジネスか
新規事業において、収益性の確保は不可欠です。どれほど優れたアイデアでも、利益が出なければ事業として継続できません。持続可能なビジネスとするためには、参入予定の分野で確実に利益を上げられる構造かを見極める必要があります。
まず、収益性を判断するには市場規模と成長性の把握が重要です。市場が縮小傾向にある場合、価格競争に巻き込まれやすく、利益を確保するのは難しくなります。一方、拡大している市場であれば、新規参入でも収益機会を得やすくなります。
次に、収益モデルの設計が鍵を握ります。製品販売だけでなく、サブスクリプション、ライセンス供与、アフターサービスといった継続的な収益源を確保する方法を検討することが求められます。あわせて、原価や運営コストの最適化によって利益率を高めることも重要です。
また、競合企業の収益構造を分析することで、収益性の高いビジネスモデルのヒントを得られます。価格設定、販路、サービス設計などを比較することで、自社に適した利益の出し方を見出すことが可能です。
このように、収益性の徹底分析は新規事業を成功に導く核心です。利益を生む構造を明確にしたうえで事業を設計すれば、安定した経営基盤の構築につながります。
実現性|自社で実行可能な体制が整うか
新規事業を成功させるには、実現可能な体制の構築が前提となります。魅力的なアイデアがあっても、自社に実行するための組織力や資源がなければ事業は成り立ちません。
まずは、自社の人材・技術・資金・業務プロセスが新規事業に対応できるかを客観的に見直す必要があります。
例えば、事業を推進するチームの編成と、必要なスキルや知見を持つ人材の確保は不可欠です。既存事業とのバランスを取りつつ、リソースの再配分や業務の再設計を行い、新規事業に集中できる体制を整える必要があります。
また、自社だけで不足する部分については、外部パートナーの活用が現実的な選択肢です。専門技術を持つ企業や業界経験の豊富なコンサルタントと連携すれば、知見を補いながらスムーズに立ち上げを進められます。
競争優位性|他社と差別化できるポイントがあるか
新規事業で成果を出すには、他社と明確に差別化できる競争優位性の確立が欠かせません。競争優位性とは、模倣が難しい技術力、独自のサービス、顧客基盤、ブランド力など、市場で自社を選んでもらうための決定的な強みを意味します。
そのためには、まず顧客にとっての「選ばれる理由」を明確にすることが必要です。たとえば、高性能な製品設計、柔軟なカスタマイズ対応、迅速なサポート体制など、競合が提供できない価値を追求することが差別化につながります。
また、優位性は一時的なもので終わらせず、継続的な改善と革新によって強化し続けることが重要です。市場の変化や顧客ニーズに対応し、新たな価値を提供し続ける企業だけが、競争環境の中で持続的に成長できます。
競争優位性の確保は、単なる付加価値の追求ではなく、自社の立ち位置を市場に定着させるための戦略的な基盤となります。
理念との整合性|経営理念やビジョンと矛盾しないか
新規事業を立ち上げる際は、自社の経営理念やビジョンとの整合性を確認することが欠かせません。
理念は企業の存在意義や価値観を示す指針であり、そこに反する事業は、社内の混乱や社外からの信頼低下を招くリスクがあります。例えば、環境重視を掲げる企業が環境負荷の高い事業に参入すれば、顧客や従業員からの支持を失いかねません。
理念と一致する事業は、企業の一貫性を保ち、ブランドの信頼性や社会的評価の向上につながります。また、社員の共感を得やすく、組織全体の士気や実行力も高まりやすくなります。反対に、理念から逸脱した事業は、方針のブレとして受け取られ、組織の統率を難しくする要因になり得ます。
したがって、新規事業の選定にあたっては、経営理念やビジョンとの整合性をしっかりと確認し、企業の方向性に合った事業を選ぶことが重要です。これにより、持続可能な成長を実現し、長期的な成功を収めることができるでしょう。
新規事業の参入分野を決めた後の進め方
新規事業への参入が決まった後は、実行に移すための具体的なステップが重要です。適切なステップを踏み、新規事業の参入をよりスムーズに進めて、成功の可能性を高めましょう。
ここでは、新規事業の参入分野を決めた後の進め方について紹介します。
重要成功要因(KSF)を明確にする
新規事業を成功に導くには、重要成功要因(KSF:Key Success Factors)を特定することが欠かせません。KSFとは、その事業において成果を上げるために不可欠な要素であり、ここを正しく押さえることで、戦略の精度と実行力が高まります。
KSFを導き出すには、まず業界の構造や市場動向を分析する必要があります。競合他社の成功・失敗事例から、有効な施策や共通する要因を抽出し、自社にとって本質的に重要な要素を見極めます。
あわせて、顧客が重視する価値(例:価格、利便性、品質、スピードなど)を把握することも重要です。顧客の期待に応えることが、事業の成果に直結するためです。
また、KSFは「具体的かつ測定可能」であることが重要です。例えば「初年度に顧客獲得数1,000件」「顧客満足度90%以上」といった数値目標を設定すれば、進捗の把握や戦略の修正が容易になります。
さらに、KSFは固定的なものではなく、市場の変化や顧客ニーズ、技術の進歩に応じて見直す必要があります。定期的なレビューと柔軟な対応を繰り返すことで、変化に強い事業基盤を築くことができます。
テストマーケティングやスモールスタートでリスクを抑える
新規事業のリスクを抑えるには「テストマーケティング」と「スモールスタート」の活用が効果的です。これらの手法は、実際の市場から反応を得ながら、事業内容や戦略を柔軟に調整することを可能にします。
テストマーケティングでは、製品やサービスを特定の地域やターゲット層に限定して提供し、顧客の反応や購買行動を検証します。この結果を基に、商品改良や価格設定、販促方法などを見直すことで、正式展開前のリスクを大幅に軽減できます。
スモールスタートは、最小限のコストと規模で事業を始め、市場の受容性を見極める手法です。例えば、ECサイトを開設する場合、まずは限られた商品数で運用を開始し、売れ筋や顧客の反応を分析しながら徐々に拡大していく戦略が有効です。
これらの方法を取り入れることで、失敗時の損失を抑えつつ、データに基づいた意思決定が可能になります。新規事業を着実に育てるためには、段階的に市場と向き合う姿勢が不可欠です。
撤退基準と数値計画を事前に決めておく
新規事業には成功の可能性と同時に失敗のリスクも伴うため、あらかじめ撤退基準と数値目標を設定しておくことが不可欠です。
撤退基準とは、期待する成果が得られなかった場合に、事業を終了する判断基準を数値で明確化したものです。これにより、損失を最小限に抑え、経営資源を他事業に有効活用できます。
例えば「半年以内に売上が○万円に達しなければ撤退を検討する」「顧客獲得単価が一定基準を超えたら戦略を見直す」といった具体的な指標を設けることで、進捗を客観的に評価できます。数値が明確であればあるほど、判断の曖昧さを排除しやすくなります。
また、数値目標の共有はチーム全体の意識統一にもつながります。達成すべき基準が明確であれば、各メンバーの行動も目的に沿ったものになりやすく、事業推進の効率が高まります。
新規事業の参入事例【5選】

新規事業への参入は、企業が市場の変化に適応し、競争力を維持するために不可欠です。他社の事例は、各企業がどのようにして新たなビジネスチャンスを見出し、成功を収めたのかを示す貴重な参考となります。
新規事業の参入を考える企業にとって、これらの成功事例から学ぶことは多いでしょう。続いて、他社の新規事業の参入事例を紹介します。
1.株式会社komham|微生物で生ごみを高速分解するスマートコンポストを開発
株式会社komhamは、2020年に札幌市で設立された環境系スタートアップ企業です。「人と地球にやさしい新しいごみ処理のスタンダードを創造する」という理念のもと、独自開発の微生物群「コムハム」を活用したスマートコンポストを提供しています。
このスマートコンポストの最大の特徴は、生ごみを最速1日で98%減量できる点です。従来の焼却処理や埋立処理に比べ、AC電源や排水処理を必要とせず、ソーラー発電で自動駆動するため、CO2の排出を大幅に削減することが可能です。また、処理データはクラウドにアップされ、利用情報をリアルタイムで取得できるため、効率的な運用が実現されています。
同社は2021年に大学ファンドから5,000万円の資金調達を実施し、渋谷区など複数の自治体でスマートコンポストが実証事業に採用されました。現在は、公共BBQ施設やイベント会場などへの設置も進めています。
2023年度中には受注販売の本格展開を予定しており、今後はバイオ技術の品質管理や専門人材の確保が課題です。komhamは、次世代の資源循環モデルの構築を目指し、環境事業の新たな道を切り拓いています。
2. ファイトケミカルプロダクツ株式会社|米ぬかからスーパービタミンEを抽出し高付加価値製品を開発
ファイトケミカルプロダクツ株式会社は、2005年に宮城県仙台市で設立された企業です。
代表の佐々木賢一氏は、地方においても東京と同様にクリエイティブな仕事環境を実現したい思いから、地域に根差した雇用の創出に取り組んでいます。新しいテクノロジーを活用し、既存サービスの刷新と未来志向の製品づくりを目指しています。
同社では、通常は廃棄される米ぬかから「スーパービタミンE(トコトリエノール)」を抽出する技術を開発しました。この技術により、健康食品や化粧品などの高付加価値製品を製造しています。健康志向の高まりに応えるとともに、未利用資源を活かすことで、環境にも配慮した持続可能なビジネスを展開しています。
創業期からは、各種補助金を活用して資金調達や優秀な人材の確保に努めてきました。さらに、自動車業界への応用も視野に入れ、大手企業との資本業務提携を進めています。
これらの取り組みにより、地域経済の活性化にも貢献しながら、事業のさらなる成長を目指しています。
3. トライポッドワークス株式会社|IoT技術を活かした車両・ドライバー管理システムを提供
トライポッドワークス株式会社は、2005年に宮城県仙台市で設立されたIT企業です。
代表の佐々木賢一氏は、外資系IT企業での経験をもとに、地元で先進的なITサービスを展開することを目指して起業しました。最新テクノロジーを取り入れ、既存サービスを進化させることで、地域に新たな価値を生み出しています。
同社は当初、オンラインストレージやネットワークセキュリティなどのオフィス向けソリューションを提供していましたが、2017年からは自動車関連のIoT分野に事業を拡大しました。
新たに提供を開始したのは、センサーを用いた車両・ドライバー管理プラットフォームです。このシステムにより、運行状況や車両の状態をリアルタイムで把握し、運転の安全性向上や業務の効率化を支援しています。
IoTを活用した同社のソリューションは、運転行動の可視化や車両メンテナンスの最適化を通じて、事故のリスク低減や燃料コストの削減につながっています。
これらの技術は運送・物流業界において高く評価されており、導入企業の業務改善と顧客満足の向上に貢献しています。また、事業の成長を通じて地域の雇用創出にもつながっており、地方経済の活性化にも寄与しています。
4.株式会社リビングロボット|教育・介護現場で使える共生型小型ロボットを開発
株式会社リビングロボットは、2018年4月に福島県伊達市で設立されたロボット開発企業です。代表の川内康裕氏は、大手家電メーカーでの製品開発経験を活かし、スピード感をもって社会課題の解決に取り組んでいます。
同社は、教育用および介護支援用の共生型ロボット「メカトロウィーゴ」を中心に、小型ロボットの開発を行っています。このロボットは、プログラミング教育や高齢者の生活支援など、多様な用途に対応しており、現場の実用性を重視して設計されています。
企業理念として、人と共に成長し、人らしい生活を支援する「活かすロボット」の実現を掲げています。
開発には、福島イノベーション・コースト構想の補助金を活用していますが、資金調達には課題もあります。ディープテック分野の特性上、金融機関による融資審査に時間がかかることが多く、安定した資金確保が事業成長の鍵となっています。そのため、通信機能を備えたスマート宅配ボックスの開発など、収益性のある新規事業にも取り組んでいます。
また、販路拡大と資本強化を目的として、2019年と2022年に第三者割当増資を実施しました。2023年にはさらなる増資を計画しており、2027年の株式上場を視野に入れ、事業の拡大を進めています。
5. 株式会社新家製作所|町工場の金属加工技術を活かし高性能コーヒーミルを開発
株式会社新家製作所は、石川県加賀市に本社を構える金属加工会社です。従来は主に金属部品の加工や組立を手掛けてきましたが、後継者不在の問題に直面し、経営承継円滑化法を活用して新社長の山下公彦氏を迎えました。
山下氏は、航空機エンジンの設計・製造経験を持ち、その技術と発想力を活かして新規事業に乗り出しました。
同社の強みは、0.1ミリ単位の精密加工を実現する熟練工の技術力にあります。これまで下請け中心だった事業構造を見直し、自社製品の開発によって新たな収益源の確立を目指しています。
現在は、その技術を応用して高性能なコーヒーミルを開発中です。独自の粉砕機構により均一な粒度を実現し、まろやかな味わいのコーヒーを抽出できる点が特長です。
試作機は安全性や清掃性にも優れ、特許も取得済みです。この製品開発は、顧客層の拡大にとどまらず、取引先や素材メーカーとの関係強化にもつながっています。
今後は、粒度調整の精度向上や外観デザインの洗練、価格設定の見直し、さらに海外特許の取得にも取り組む予定です。町工場の技術をもとに新たな市場を開拓する姿勢が、地域産業の持続的発展に貢献しています。
戦略から実行までを一気通貫で商売繁盛支援
縁達磨では、ブランド戦略やマーケティング戦略立案などの上流工程から獲得施策の下流工程を自社で一気通貫で支援することで、足元の販売効率を上げながら、未来の競争力をタマける統合型マーケティング支援が強みです。
事業領域を特化させ、専門性を高めることが主流となっていますが、事業環境がますます複雑化する中で「商売繁盛の縁を引き起こす」という使命を遂行するためには、上流工程から下流工程までを全方位でご支援し、全体最適をしていく必要があると考えているため、このような体制を敷いています。
商売の悩みをいつでも気軽にご相談ください。
新規事業への参入は、企業が変化する市場に対応し、成長を継続するうえで欠かせない取り組みです。そのためには、収益性や実現性、市場の成長性に加え、自社の強みや経営理念との整合性を踏まえた戦略的な判断が求められます。
成功事例からは、リスクを抑える工夫や現場の知見を活かした展開の重要性も見えてきます。変化を恐れずに挑戦を重ねていくことこそが、企業の未来を切り開く原動力になります。
縁達磨では、売場とコミュニケーション施策から逆算した「売りやすい」事業/商品設計を得意としています。Amazon売れ筋1位獲得、TV特集番組6件、広告費ゼロで初月売上1000万、海外販路獲得するなど、これまで7つの開発実績があります。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.