
2025.07.11
新規事業の立ち上げに必要なことは?必要なスキルやプロセスも紹介
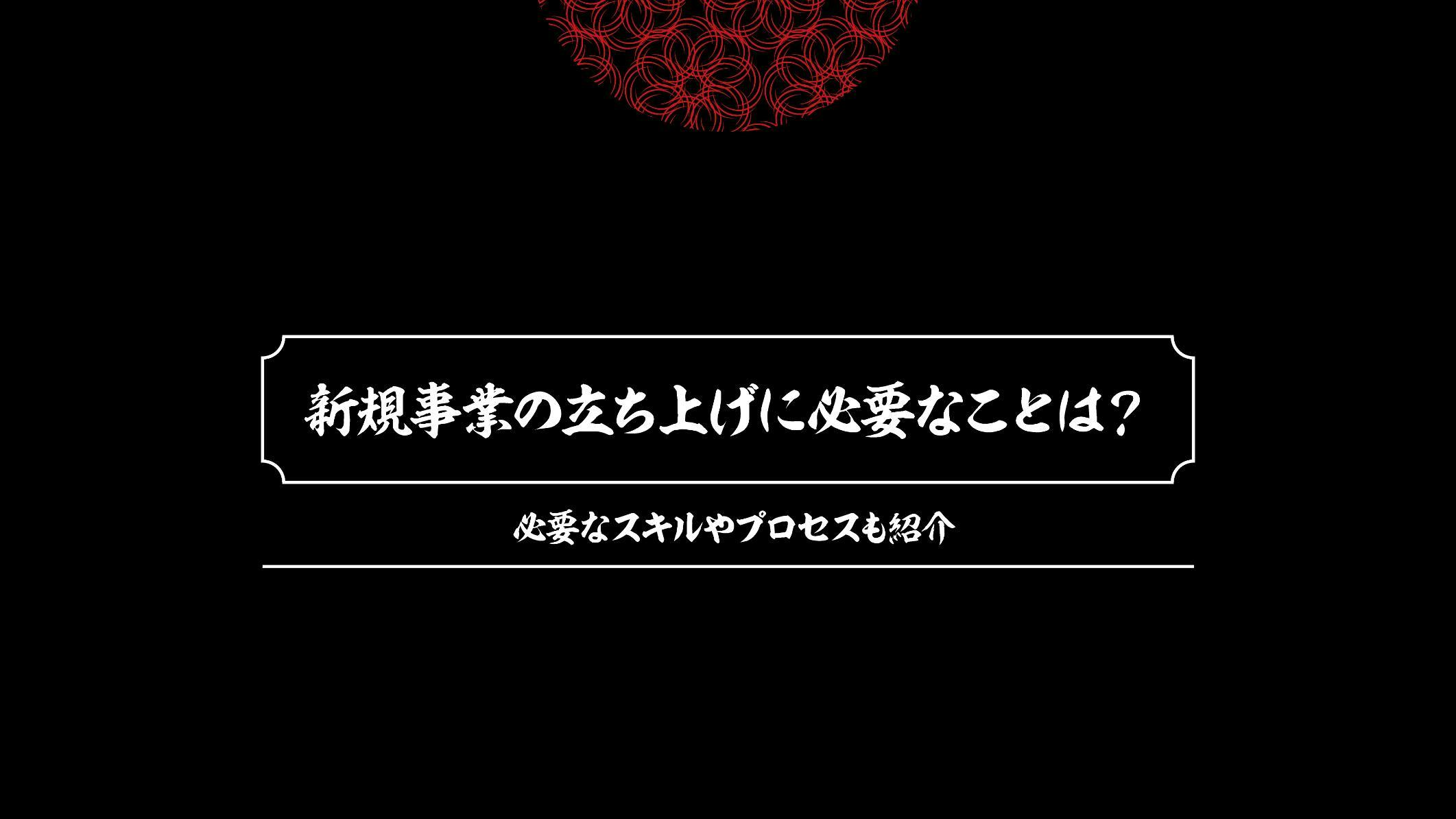
市場の変化が激しい今、企業にとって新規事業の立ち上げは持続的成長の鍵となっています。しかし、ゼロから事業を生み出すには、明確なプロセスと必要なスキルを押さえておくことが欠かせません。
本記事では、新規事業が求められる理由から、立ち上げに必要な準備・スキル・プロセス・活用できるフレームワークまでをわかりやすく解説します。
新規事業の立ち上げが求められる理由

新規事業の立ち上げは、企業にとって多くのメリットをもたらします。市場の変化に柔軟に対応し、社員の成長を促して、持続的な成長を実現しましょう。
ここでは、新規事業の立ち上げが求められる理由について紹介します。
時代の変化に備えてリスクを分散できる
新規事業の立ち上げは、変化の激しい市場環境に対応するための有効な手段です。テクノロジーの進化や消費者ニーズの多様化により、既存のビジネスモデルだけでは安定した成長を維持することが難しくなっています。
既存の製品や市場に依存している企業は、経済の変動や競合の台頭によって業績が大きく左右されるリスクを抱えています。新規事業によって異なる分野や顧客層に展開すれば、収益構造の多角化が進み、特定領域への依存を減らすことができます。
加えて、新たな挑戦はイノベーションを生み出し、社員の学習意欲や当事者意識を高める効果もあります。これにより、組織全体の柔軟性と成長力が向上し、長期的な競争優位の確立にもつながります。
社員が育つ機会をつくれる
新規事業の立ち上げは、企業の成長だけでなく、社員にとっても実践的な学びの場となります。新しいプロジェクトへの参加を通じて、業務スキルの向上に加え、未知の領域での経験や視点を得ることができます。これにより、問題解決力や創造力といった応用的な能力が自然と鍛えられます。
また、チームでの業務が多くなるため、他部署との連携や社内のコミュニケーションが活性化し、組織全体の連帯感が高まります。自分の意見が事業に反映される環境では、社員の主体性や意欲も引き出されやすくなります。
さらに、プロジェクトを推進する中で、リーダーシップやマネジメントの経験を積むことができ、次世代の管理職や経営層を育てる土壌にもなります。新規事業は、社員の成長と組織の強化を同時に実現する貴重な機会といえるでしょう。
新規事業の立ち上げに必要なこと

新規事業を成功させるためには、いくつかの重要な要素を押さえておく必要があります。これらの要素を総合的に考慮し、新規事業の立ち上げに向けた準備を進めることが、成功への第一歩となるでしょう。
ここでは、新規事業の立ち上げに必要なことについて紹介します。
リソースの活用・調達方法を見定める
新規事業を成功させるには、限られたリソースをどう使い、どのように補うかを見極めることが欠かせません。
まずは、自社にある人材・資金・技術・情報などのリソースを把握し、それぞれの強みを最大限に活かす方法を検討しましょう。社内で賄えない部分については、外部からの補完も視野に入れる必要があります。
例えば、他企業との提携によって新たなノウハウや技術を導入したり、クラウドファンディングや投資家からの出資によって資金を調達したりする方法があります。こうした外部リソースの活用は、事業のスピードや柔軟性を高める手段となります。
ただし、短期的なコスト削減や即効性だけにとらわれると、長期的な持続性を損なうリスクもあります。リソース調達ではコスト・リターン・リスクのバランスを慎重に見極め、中長期の成長に資する判断が求められます。
未来の情報を戦略に取り込む
新規事業の成功には、変化する市場や社会の動きを先読みする力が欠かせません。消費者ニーズや技術の進化に対応するためには、未来を見据えた情報収集と戦略への反映が必要です。
そのためには、業界の動向、競合の動き、新技術の進展などを継続的にチェックし、自社の方針や商品企画に反映させることが重要です。特に、ビッグデータやAIを活用すれば、顧客の行動や市場変化を予測しやすくなり、的確な判断が可能になります。
また、業界の有識者や先進企業とのつながりを持つことで、定量データでは見えない現場のリアルな情報も得られます。セミナーやワークショップを通じて最新事例やトレンドを取り入れれば、時代の変化に強い事業戦略を築くことができるでしょう。
行政や異業種との協働を進める
新規事業を進めるうえで、行政や異業種との連携は有効な手段です。行政機関と協力することで、補助金・助成金などの支援制度を活用でき、資金面の負担を軽減できます。
また、地域の課題や政策と連動させた事業展開も可能となり、社会的な信頼性の向上にもつながります。行政が主催するセミナーや交流イベントに参加すれば、他の企業や専門家とのネットワークづくりができ、新たな知見やビジネスチャンスを得る機会にもなります。
さらに、異業種との協働は、これまでにないアイデアや技術を取り入れる手段として有効です。異なる業界の知見と自社の強みを組み合わせることで、革新的な商品やサービスの開発につながり、市場での競争力を高めることができます。
補助金や助成金を活用する
新規事業では資金調達が大きな課題となりますが、補助金や助成金を活用することで初期コストを抑えることが可能です。これらは国や自治体が特定の条件を満たす事業に対して提供する資金支援であり、返済の必要がないため資金繰りの安定化に役立ちます。
まずは、自社の事業に適した制度を把握することが重要です。地域や業種、事業目的に応じて多様な支援メニューがあり、特に新規事業や技術革新を対象とした制度が多く用意されています。情報収集は自治体のウェブサイトや商工会議所、支援機関を通じて行いましょう。
申請にあたっては、事業計画書や資金計画などを明確に示す必要があります。制度ごとに申請条件や提出書類、期限が異なるため、早めに準備を進めることが採択の可能性を高めるポイントです。
テクノロジーを取り入れる
新規事業を成功させるには、テクノロジーの活用が欠かせません。デジタル化が進む現在、技術の導入は業務効率の向上だけでなく、競争力の強化にも直結します。
例えば、データ分析を用いれば、顧客の行動や市場の変化を把握し、精度の高い戦略立案が可能になります。AIの導入により、業務の自動化や予測分析が実現でき、人的リソースを創造的な業務に振り向けることもできます。
さらに、クラウドサービスを活用すれば、大規模な初期投資を抑えつつ、必要な機能を柔軟に取り入れられ、事業の拡張性も高まります。
テクノロジーの導入は効率化にとどまらず、新たな価値の創出や顧客体験の向上にもつながります。変化の早い市場で優位に立つためにも、戦略的な技術活用が求められます。
マーケティングで事業成長を後押しする
新規事業の成功には、戦略的なマーケティングが不可欠です。競争が激しい市場において、ターゲットを明確にし、顧客に響くメッセージを届けることが事業の成長を左右します。
まず、ターゲット層のニーズや行動を把握し、それに応じた訴求内容やチャネルを選定することが重要です。特にデジタルマーケティングは、SNSや検索広告を活用することで、低コストかつ広範囲にアプローチできます。
さらに、コンテンツマーケティングやSEO施策によって、検索経由での自然な流入を増やし、ブランド認知や信頼感の向上にもつなげられます。
顧客との継続的な関係構築も成長の鍵です。アンケートやフィードバックをもとに商品やサービスを改善すれば、顧客満足度が高まり、リピート率の向上にもつながります。
最後に、マーケティング施策の効果を定期的に分析し、改善を重ねることが重要です。データに基づいた柔軟な見直しが、持続的な事業成長を支える基盤となります。
新規事業をスムーズに立ち上げるための8つのプロセス
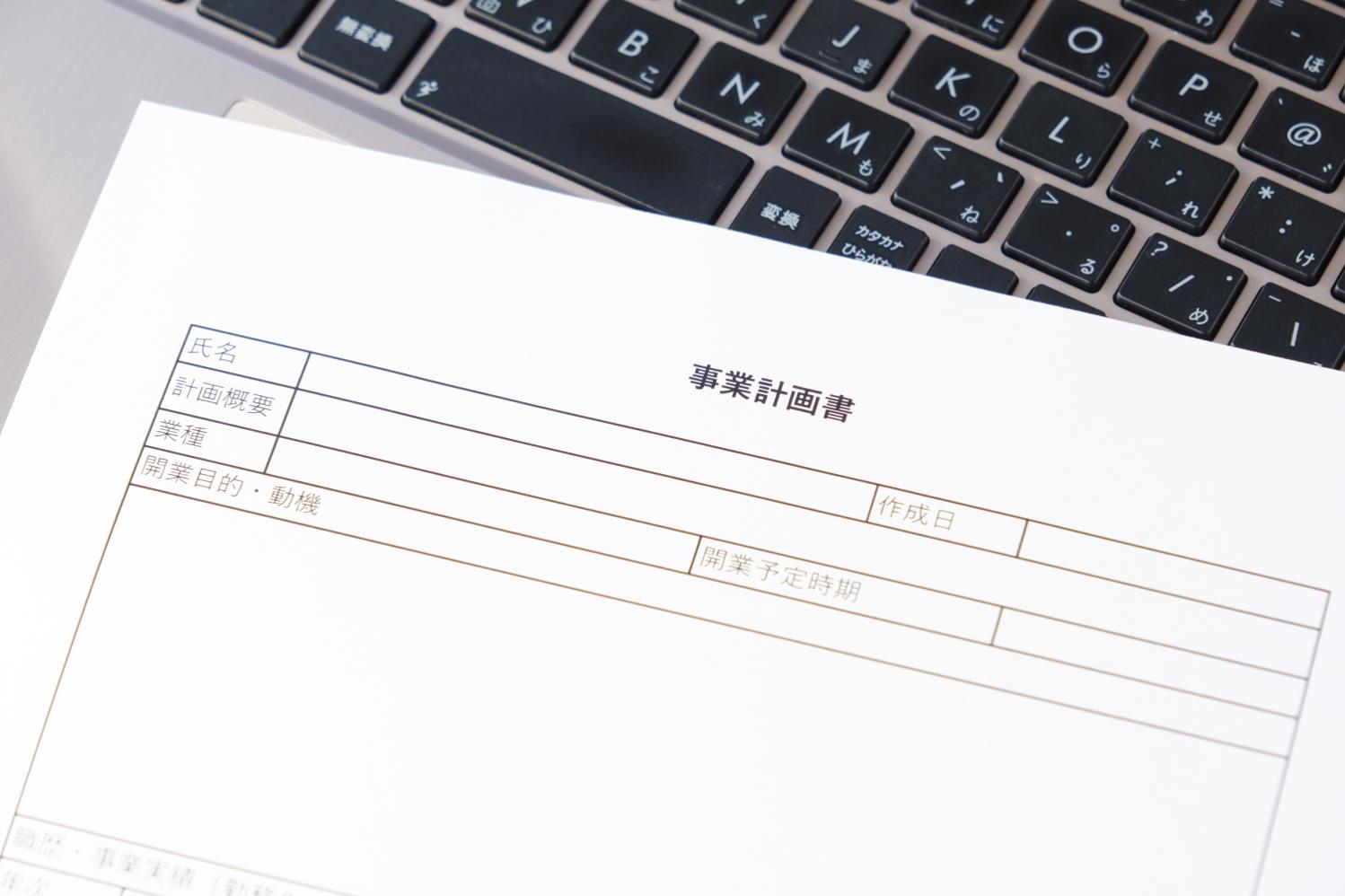
新規事業の立ち上げは、計画的かつ段階的に進めることが成功の鍵となります。適切なプロセスを順に進めることで、新規事業の立ち上げをより効果的に行えるでしょう。
ここでは、新規事業をスムーズに立ち上げるための8つのプロセスについて紹介します。
1. アイデアを生み出す
新規事業の第一歩は、価値あるアイデアの創出です。単なる思いつきではなく、課題解決やニーズに基づいた実現可能な企画へと落とし込む必要があります。
ここで役立つのが、縁達磨が売れている商品やキャンペーンなどの分析を通して見つけた「すえひろがり企画法」です。この手法では、下記8つの評価軸を使い、企画の魅力や広がりを多角的に検証します。
- 新規性
- 意外性
- 娯楽性
- 社会性
- 自流性
- 実績性
- 優位性
- 人物性
例えば、若年層向けの新サービスであれば「娯楽性×自流性×人物性」を重視するなど、目的に応じた軸の取捨選択も可能です。このプロセスにより、共感性と話題性を兼ね備えた広がる企画へとつながります。
2. 市場を調査する
市場調査は、顧客のニーズや競合状況、業界動向を把握し、事業の方向性を定めるために不可欠です。まず、アンケートや統計から購買傾向や市場規模などの定量データを収集し、根拠ある判断材料とします。
次に、インタビューやフォーカスグループを通じて、顧客の本音や潜在的な課題を把握することが重要です。さらに、競合の強みや戦略を分析することで、自社の差別化要素を明確にできます。
3. 計画を立てる
事業計画は、目指す方向と達成手段を明確にする設計図です。まず、ビジョンやミッションを定めたうえで、短期・長期の目標を数値で設定し、行動指針を具体化します。
次に、市場や競合の分析結果をもとに、自社の強みを活かした戦略を立案し、必要な人材・資金・時間などのリソースを適切に配分します。
加えて、リスクの洗い出しと対応策も計画に盛り込み、実行段階での混乱を防ぎます。変化に備えて、状況に応じた見直しが可能な柔軟性も確保しておくことが重要です。
4. 資金を調達する
新規事業には資金の確保が不可欠です。自己資金は外部からの信用力向上にもつながるため、最初に検討すべき手段です。
銀行融資を受ける際は、事業計画と返済計画を明確に示すことが重要です。成長性の高い事業であれば、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルの出資を受けられるでしょう。
さらに、クラウドファンディングを活用すれば、少額の出資を広く集めながら市場の反応も確認できます。事業の特性や資金ニーズに応じて、最適な手段を選択してみてください。
5. 組織・事業体を設立する
新規事業には、運営の土台となる組織や法人の設立が欠かせません。まず、事業の目的やビジョンを明確にし、それに基づいて必要な人材や部門構成を決定します。
次に、株式会社や合同会社など適切な法人形態を選び、登記や許認可などの法的手続きを行います。専門家に相談することで手続きの精度と効率を高められます。
加えて、組織文化や価値観の共有を図ることで、チーム全体が同じ目標に向かって動きやすくなります。資金調達計画も並行して立て、持続可能な運営体制を整えることが重要です。
6. 商品・サービスを開発する
新規事業では、商品やサービスを具体化し、市場投入できる形にする開発プロセスが重要です。まず、ターゲット顧客のニーズを明確に把握し、それに基づいてコンセプトを設計します。
次に、初期段階でプロトタイプを作成し、ユーザーからのフィードバックを通じて機能や使い勝手を検証・改善します。開発は一人で完結せず、異なる専門性を持つチーム内の意見を取り入れることで品質が高まります。
7. 販売・プロモーションを行う
商品やサービスを市場に投入する段階では、販売戦略とプロモーション施策の設計が不可欠です。まず、ターゲット顧客を明確にし、ニーズや購買行動を把握したうえで、最適なメッセージと訴求方法を決定します。
販売チャネルは、ECサイト、実店舗、代理店などから適切に選定し、商品の特性や顧客の購買導線に合致させることが重要です。プロモーションでは、SNS広告、検索連動型広告、イベントなどを組み合わせ、費用対効果を意識した展開を図ります。
また、コンテンツマーケティングやインフルエンサーの活用によって、認知拡大と信頼構築を効率的に進められます。施策の効果は定期的に分析し、データをもとに改善を重ねることで、販売活動の精度と成果を高めていきます。
8. 効果を検証・改善する
新規事業を継続的に成長させるには、施策の効果検証と改善が不可欠です。まず、設定したKPIに基づいて売上や顧客反応、広告効果などのデータを収集・分析し、実行した施策の成果を把握します。
分析結果から、効果的だった要因や課題を明確化し、改善策を立案します。例えば、顧客の声を反映した商品改良や、訴求不足だったプロモーション内容の見直しが挙げられます。
また、競合の動向や市場の変化にも目を向け、柔軟に戦略を修正することが重要です。こうした検証と改善を定期的に繰り返すことで、事業の精度が高まり、継続的な成長と収益性の向上につながります。
新規事業の立ち上げに必要なスキル

新規事業を成功させるには、特定のスキルが不可欠です。スキルを身につけて、新規事業の立ち上げをよりスムーズに進めましょう。
続いて、新規事業の立ち上げに必要なスキルを紹介します。
柔軟な発想で新たな可能性が引き出せる
新規事業では、変化する市場や多様なニーズに対応するため、柔軟な発想が不可欠です。既存の枠組みにとらわれず、異業種の成功事例や他分野の知見を応用することで、新たなビジネスの可能性が見出せます。
チーム内でも自由に意見を出し合える環境を整えることで、多角的な視点が集まり、創造的なアイデアが生まれやすくなります。ブレインストーミングやワークショップの活用も有効です。
また、失敗を前提とした試行錯誤を恐れず、柔軟に戦略を調整する姿勢が、継続的な改善と成長につながります。
関係者と連携しながら調整を進められる
新規事業を成功に導くには、社内外の関係者との連携が欠かせません。部署間で情報やリソースを共有し、営業・開発・マーケティングが一体となって動くことで、戦略の整合性が高まります。
定例ミーティングや進捗確認を通じて意見交換を行えば、部門間のずれを防ぎ、目標達成に向けた調整がしやすくなります。
また、顧客や外部パートナーからのフィードバックを柔軟に取り入れることも重要です。ニーズや市場の変化を反映した対応ができれば、事業の方向性を的確に修正できます。
異業種との連携も、新たな発想や知見を取り込む手段として有効です。
アイデアを形にし、行動へ移せる
新規事業では、アイデアを形にし行動へつなげる力が不可欠です。思いつきを事業に変えるには、目的を明確にし、具体的な価値や成果を定義することが出発点となります。
その上で、実現に必要なリソースやスキルを洗い出し、短期・長期の目標に基づいた実行計画を策定します。進捗を定期的に見直し、柔軟に修正することで、計画の精度と実効性が高まります。
また、関係者と密に連携しながら意思決定を進めることで、現実的かつ効果的なアクションに落とし込むことが可能になります。こうしたプロセスを通じて、アイデアは実行可能な事業へと昇華します。
不確実な状況でも判断し、課題を解決できる
新規事業では、計画通りに進まない不確実な状況に直面することが避けられません。市場の変動や顧客ニーズの変化に対応するには、柔軟な思考と迅速な判断力が必要です。
まず、正確な状況把握のために情報を集め、課題を特定し、優先順位をつけて対応策を検討します。定量データや現場の声を根拠にすることで、判断の精度が高まります。
また、チーム内の意見交換を通じて多角的な視点を取り入れることで、効果的な解決策を導きやすくなります。加えて、失敗を恐れず新しい手法を試す姿勢も、変化の激しい環境下では有効です。
新規事業を加速させるためのフレームワーク活用術
新規事業の立ち上げにおいて、フレームワークを活用することは非常に重要です。フレームワークは、複雑なプロセスを整理し、効率的に進めるための道筋を提供してくれます。
ここでは、特に役立つフレームワークの活用術をいくつか紹介します。
アイデア創出に活かせる発想法
新規事業において、実現可能なアイデアを創出することは出発点となります。的確な発想法を使えば、より効果的にアイデアを生み出すことが可能です。
まず、ブレインストーミングは代表的な手法です。批判を避けて自由に意見を出し合うことで、予想外の着想が得られる場合があります。アイデアの量を重視することで、後から有望な案を選びやすくなります。
次に、マインドマップは思考の整理に役立ちます。中心にテーマを置き、そこから関連語句を展開することで、視点の広がりや隠れた関係性が明確になります。
また、逆転発想も有効です。常識とは逆の問いを立てることで、潜在的なニーズや新たな視点が得られます。例えば「なぜ顧客は購入をためらうのか?」と考えることで、改善のヒントを導けます。
複数の手法を併用することで、多角的なアイデア創出につながり、事業化への一歩を確実に踏み出すことができます。
市場環境を読み解く分析手法
新規事業を成功させるには、市場環境の的確な分析が不可欠です。動向や競合の状況を把握することで、戦略の精度が高まり、リスクへの備えも強化されます。
まず、PEST分析は外部環境を評価する基本手法です。下記の4視点から、市場に影響を与える外的要因を整理します。
- 政治(Political)
- 経済(Economic)
- 社会(Social)
- 技術(Technological)
これにより、規制や経済情勢など、事業に影響する要素を早期に把握できます。
次に、SWOT分析では、自社の強み・弱みと市場の機会・脅威を明確にします。自社がどの分野で優位性を持ち、どの点を改善すべきかを客観的に把握でき、戦略立案の基盤になります。
さらに、競合分析も欠かせません。競合他社の製品、価格設定、販売手法を調査することで、自社の差別化ポイントを見つけ出すことができます。成功事例や失敗例を比較し、実行可能な施策へと落とし込むことが重要です。
ビジネスモデルを設計するためのツール
新規事業の立ち上げにおいて、ビジネスモデルの設計は非常に重要なステップです。適切なツールを活用することで、アイデアを具体化し、実現可能なビジネスモデルを構築することができます。
まず、ビジネスモデルキャンバスは、視覚的にビジネスモデルを整理するための強力なツールです。このキャンバスを使うことで、下記のようなビジネスの主要要素を一目で把握することができます。
- 顧客セグメント
- 価値提案
- チャネル
- 収益の流れ など
チームでのブレインストーミングや戦略会議においても、キャンバスを用いることで意見を集約しやすくなります。
次に、リーンキャンバスも注目すべきツールです。特にスタートアップや新規事業において、リスクを最小限に抑えながら迅速に検証を行うために設計されています。
リーンキャンバスは、下記を簡潔にまとめることができ、仮説を立てて実際の市場での反応を確認する際に役立ちます。
- 問題
- 顧客セグメント
- 解決策
- 収益の流れ など
マーケティング戦略を整理する枠組み
新規事業の立ち上げにおいて、マーケティング戦略は成功の鍵を握る重要な要素です。効果的なマーケティング戦略を構築するためには、いくつかのフレームワークを活用することが有効です。
まず、代表的なものとして「4P(Product・Price・Place・Promotion)」があります。このフレームワークは、製品やサービスの特性、価格設定、流通経路、プロモーション手法を整理し、ターゲット市場に最適なアプローチを見つけるのに役立ちます。
次に「STP(Segmentation・Targeting・Positioning)」のフレームワークも重要です。
市場をセグメント化し、ターゲットを絞り込んだうえで、自社製品やサービスの立ち位置を明確にすることで、より効果的なマーケティング戦略を立てることができます。顧客ニーズに合わせたメッセージも伝えやすくなります。
さらに「カスタマージャーニー」を用いれば、購買に至るまでの顧客行動を可視化でき、接点ごとの最適な対応策を設計できます。これらの枠組みを組み合わせることで、説得力のあるマーケティング戦略が構築できます。
進捗管理と成果検証に役立つ指標
新規事業の立ち上げにおいて、進捗管理と成果検証は非常に重要な要素です。
事業が計画通りに進んでいるかを把握するためには、適切な指標を設定し、定期的に評価することが不可欠です。これにより、問題点を早期に発見し、必要な修正を行うことが可能になります。
まず、進捗管理においては、KPI(重要業績評価指標)を設定することが基本です。
KPIは、事業の目標達成度を測るための具体的な数値であり、売上高や顧客獲得数、リピート率などが一般的に用いられます。これらの指標を定期的にモニタリングすることで、事業の健康状態を把握しやすくなります。
次に、成果検証にはROI(投資対効果)やCAGR(年平均成長率)などの指標が役立ちます。ROIは、投資に対する利益を測るもので、事業の収益性を評価する際に重要です。一方、CAGRは一定期間における成長率を示し、長期的な視点での事業の成長を把握するのに役立ちます。
さらに、顧客満足度やNPS(ネットプロモータースコア)などの定性的な指標も重要です。これらは、顧客の声を反映し、事業の方向性を見直すための貴重な情報源となります。
定量的なデータと定性的なデータを組み合わせることで、より包括的な評価が可能となり、事業の改善に繋がります。
戦略から実行までを一気通貫で商売繁盛支援
縁達磨では、ブランド戦略やマーケティング戦略立案などの上流工程から獲得施策の下流工程を自社で一気通貫で支援することで、足元の販売効率を上げながら、未来の競争力をタマける統合型マーケティング支援が強みです。
事業領域を特化させ、専門性を高めることが主流となっていますが、事業環境がますます複雑化する中で「商売繁盛の縁を引き起こす」という使命を遂行するためには、上流工程から下流工程までを全方位でご支援し、全体最適をしていく必要があると考えているため、このような体制を敷いています。
商売の悩みをいつでも気軽にご相談ください。
新規事業の立ち上げは、変化の激しい時代を乗り越えるための重要な選択肢です。柔軟な発想力や実行力を備えた人材の育成、行政や異業種との連携、テクノロジーの活用など、さまざまな視点からの準備が成功を左右します。
段階的なプロセスとフレームワークを活用すれば、アイデアの着想から事業化までの流れを着実に進めることができます。新たな価値を創出するために、今こそ一歩を踏み出しましょう。
縁達磨では、売場とコミュニケーション施策から逆算した「売りやすい」事業/商品設計を得意としています。Amazon売れ筋1位獲得、TV特集番組6件、広告費ゼロで初月売上1000万、海外販路獲得するなど、これまで7つの開発実績があります。
少しでも縁達磨へ興味を持って頂けましたら、ぜひ気軽にご相談ください!
縁達磨でご支援できないと判断した場合でも、喜んで信頼できるパートナーをご紹介します。
商売繁盛の縁を引き起こせるよう、一生懸命がんばります。
ご縁に感謝。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら : お気軽にお問い合わせください。
Drop us a line.